相続放棄は被相続人の負債をキャンセルできる大きなメリットをもつ制度ですが、メリットの一方で気をつけるべきデメリットもあります。
メリットだけを見て相続放棄をしてしまうと、取り返しのつかないことになるかもしれません。
この記事では安易な相続放棄によってかえって損をしてしまわないためにも、「相続放棄のデメリット」について、制度の基本から実際に起こりうるリスク、よくあるケースまでを詳しく解説します。
相続放棄の主なデメリット

相続放棄には被相続人が残した負債を負わずに済む大きなメリットがありますが、一方で気をつけるべきデメリットもあります。
相続放棄の主なデメリットとして以下の8つがあります。
- マイナスの財産だけではなくプラス財産も放棄することになる
- 一度相続放棄を選択すると撤回できない
- 相続放棄すると相続権が次順位に移行し、他の相続人に負担がかかる
- 相続放棄をしても他の相続人が現れるまでは財産管理の義務が残る
- 遺品整理や金融手続きができなくなる
- 遺族年金や死亡退職金などが受け取れない可能性がある
- 扶養義務が免除されない可能性がある
- 相続放棄手続きにも手間と費用がかかる
それぞれ詳しく解説します。
マイナスの財産だけではなくプラス財産も放棄することになる
相続放棄をすると、借金や買い手の見つからない土地など、マイナス財産の相続をすべて放棄することができますが、同時に預貯金や建物などのプラス財産まで一切相続できなくなります。
深く考えずに、マイナス財産を相続したくない一心で相続放棄を選んでしまうと、価値のある財産まで手放すことになってしまいます。
後からプラスの財産が見つかったとしても撤回はできないため、相続放棄の決断には熟慮が必要です。
一度相続放棄を選択すると撤回できない
相続放棄は原則として、一度手続きが完了すると撤回できません。
| 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。 引用元:民法第919条第1項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) |
撤回ができないルールは、相続関係の安定化を図りつつ、後の紛争を避けるための処置でもあります。
たとえば、相続放棄した後に莫大な遺産が見つかると、「やっぱり相続放棄は撤回します」と言いたくなりますが、そのような理由では撤回は認められません。
相続放棄の撤回が認められるケースは、詐欺や脅迫によって相続放棄をせざるを得なかった場合など、法的な問題があった場合に限定されます。
相続放棄の撤回には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
また、相続放棄には「期限」がある点にも注意が必要です。
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければなりません。
| 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 引用元:民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間) |
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、これを過ぎてしまうと、単純承認(負債を含めすべてを相続)したものとみなされてしまいます。
このように相続放棄は撤回ができないだけでなく、期限の過ぎた放棄は無効となる点にも注意しましょう。
相続放棄すると相続権が次順位に移行し、他の相続人に負担がかかる
他の相続人と打ち合わせもなく勝手に相続放棄をしてしまうとトラブルに発展する可能性が高まります。
相続放棄した分の遺産は、他の相続人が負担しなければいけません。
プラス財産ならまだしも、大きな負債を何の相談もなく負わされると、不満が生じる可能性があります。
相続放棄をした人が、被相続人の生前に特別な利益を受けていた場合、他の相続人からの不満はかなりのものとなるでしょう。
相続放棄をした場合、その旨を他の相続人へ通知する義務はありませんが、後々のトラブルを回避するためにも、事前の相談と打ち合わせは必要です。
複数の相続人が放棄すると、財産処分に時間がかかることがあるので注意
被相続人の子ども全員が相続放棄した場合、次の相続順位は被相続人の父母、父母が相続放棄すると次は兄弟姉妹へ相続権が移動します。
このように相続権が転々としてしまうと、誰が相続人になるのか確定までに時間がかかってしまい、その間は不動産の売却や預貯金の払い戻しができません。
最終的に家庭裁判所が相続財産管理人を選ぶまで、何も手をつけられなくなります。
相続放棄をしても他の相続人が現れるまでは財産管理の義務が残る
相続放棄をした場合でも、相続人であった者がすでに相続財産を占有していた場合には、次の管理者に引き渡すまで引き続き管理義務を負います。
これは、民法第940条第1項に基づく義務です。
| 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 引用元:民法第940条第1項(相続の放棄をした者による管理) |
相続放棄をしても一定期間は「管理者」としての責任が継続されます。
特に、相続人全員が放棄してしまい、相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されるまでの間は、その相続財産を放置することができず、管理義務が発生し続けます。
たとえば、空き家などの不動産を放置していて倒壊や火災、不法投棄などのトラブルが発生した場合、元相続人である放棄者に管理責任を問われる可能性もあるのです。
このように、「相続放棄をすればすべて関係なくなる」と誤解していると、思わぬ損害賠償リスクを負うおそれもあるため、相続放棄後の管理義務についても正しく理解しておきましょう。
遺品整理や金融手続きができなくなる
相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、被相続人の遺品を整理したり金融機関で口座の解約をしたりなどの手続きは原則できません。
遺品や金融手続きに手をつけると、相続財産の処分をしたことになり、相続を承認したとみなされる可能性があります。
相続放棄をした立場から遺品整理を行いたい場合は、他の相続人へ依頼するか、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければいけません。
金融手続きについても同じく、相続財産管理人を通して手続きを進める必要があります。
遺族年金や死亡退職金などが受け取れない可能性がある
相続放棄をしても、遺族年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利とされているため、基本的には受け取ることができます。
遺族年金の支給対象者(受給資格者)は、被保険者との生計を共にしていたかどうかや、「配偶者・子・父母・孫・祖父母」の優先順位などの要件によって決まります。
そのため、相続放棄の有無にかかわらず、制度上の要件を満たしていれば受給可能です。
一方で、死亡退職金については、企業の規定や遺族給付制度の内容により異なります。
たとえば、受取人が「相続人」とされている場合には、相続放棄によって受給資格を失う可能性があります。
しかし、「配偶者」や「子」など特定の個人が明示されている場合は、その人の固有の権利とみなされ、相続放棄の影響を受けないのが一般的です。
制度ごとに異なる取り扱いとなるため、実際に判断する際は保険者(年金機構など)や企業・勤務先に確認することをおすすめします。
扶養義務が免除されない可能性がある
相続放棄は、被相続人の財産に関する権利や義務を放棄する制度です。
しかし、相続人自身の親族に対する扶養義務と相続放棄は別問題である点には注意が必要です。
民法第877条に基づき、直系血族および兄弟姉妹の間には扶養義務が発生します。
| 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 引用元:民法第877条第1項(扶養義務者) |
これは相続とは無関係であり、相続放棄をしても扶養義務が免除されるわけではありません。
さらに、相続放棄が生活保護制度に与える影響も見逃せません。
たとえば、自分の親が生活保護を受けている場合、相続放棄をしても扶養照会(扶養できるかどうかの確認)が行われる可能性があります。
そのため、自分の親が生活保護を受けている場合は、「相続放棄=扶養義務の免除」とはならないことを、事前に理解しておくことが重要です。
相続放棄手続きにも手間と費用がかかる
相続放棄の手続きには家庭裁判所への申し出が必要です。幾つかの書類を集めて、作成しなければいけません。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、申述人の戸籍謄本などです。
手続きに必要な書類を取得するには手数料も必要です。
参考記事:相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや知っておきたい注意点を紹介
書類の取得費用の他には、家庭裁判所への郵送費用や、専門家へ依頼する場合には報酬も用意しなければいけません。
相続放棄は、単に相続の意思を表明するだけでは終わらないことを認識しておく必要があります。
書類の取得費用と相続放棄にかかる時間を逆算して、計画的に進めることが大切です。
【ケース別】相続放棄のデメリット
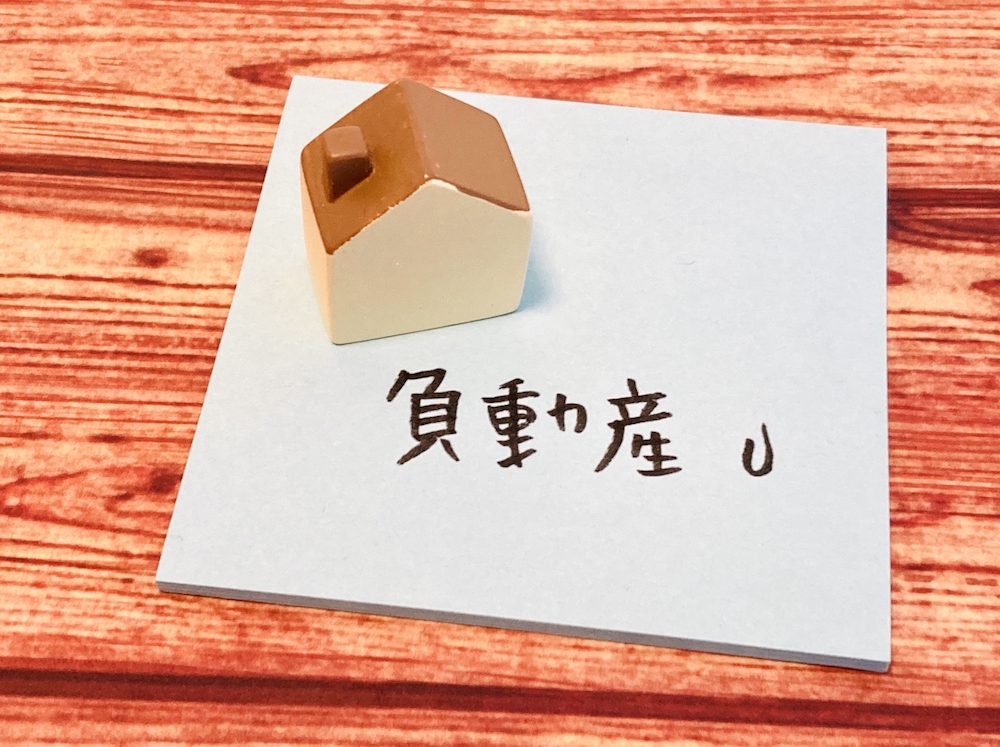
相続放棄のデメリットはケース別のイレギュラーパターンもあります。
より悩み事への具体的な回答を示すために、ケース別のデメリットをまとめてみました。
- 親の相続を放棄した場合
- 配偶者の相続を放棄した場合
- 相続財産に空き家や山林がある場合
- 事業用資産が相続財産に含まれる場合
- 相続人が高齢者や未成年の場合
5つのケースについて詳しく解説します。
親の相続を放棄した場合
親の相続を放棄した場合に考えられるデメリットとして、以下の3つがあります。
- 遺言の効力が相続放棄者には及ばない場合がある
- 実家に住めなくなる
- 家の名義変更が自分ではできなくなる
遺言の効力が相続放棄者には及ばない場合がある
相続放棄をした人が、遺言書で相続人として特定の財産を受け取るよう指定されていた場合でも、相続放棄によってその効力は失われます。
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるためです。
| 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 引用元:民法第939条(相続の放棄の効力) |
相続人としての立場による遺贈(包括遺贈など)は受け取ることができません。
ただし、遺言書で「〜に財産を与える」など、相続人ではない第三者として受遺者に指定されていた場合は、相続放棄をしていても遺産を受け取れる可能性があります(※特定遺贈に該当)
このように、遺言書の効力が及ぶかどうかは、相続人として指定されているか、第三者(受遺者)として指定されているかによって変わるため、遺言書の内容の確認が重要です。
実家に住めなくなる
親の遺産相続を放棄した場合、法的に相続人でなくなることから、実家に対する権利を主張することができなくなります。
他の相続人は実家の処分を自由にできるため、他の相続人が実家を売却してしまうと、住み続けることはできません。
たとえば、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が実家を売却して遺産分割をすると決めた場合、退去を迫られます。
長年住み慣れた実家でも、相続放棄をした以上、他の相続人の決定には従わなければいけません。
家の名義変更が自分ではできなくなる
相続放棄をすると法的に家の所有者ではなくなるため、自分で自由に名義変更することができません。
ただし、家の名義が故人のままになっている場合、行政上の事務処理として、相続放棄をした人にも固定資産税の納付書が届くことがあります。
相続放棄をした人に法的な納税義務はありませんが、支払いを求められるケースもあるため、注意が必要です。
このように、相続放棄をして名義変更や売却ができない状態にもかかわらず、税金などの負担が発生することがあり、状況によっては板挟みのような状態に陥ることもあります。
配偶者の相続を放棄した場合
配偶者の相続を放棄した場合に考えられるデメリットとして、以下の3つがあります。
- 子供に相続権が移る
- 配偶者の口座が凍結され、引き出せなくなる
- 家に住めなくなる可能性がある
順番に見ていきましょう。
子どもに相続権が移る
配偶者の相続を放棄した場合、負債を含む相続財産は第一順位の相続人である子どもが相続することになります。
もし配偶者に借金などの負債がある場合、負債を引き継ぐのは子どもです。
何も知らずに相続放棄をしてしまうと、子どもが経済的な負担を強いられる可能性があります。
参考記事:相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや知っておきたい注意点を紹介
配偶者の口座が凍結され、引き出せなくなる
配偶者が亡くなると、金融機関は相続財産の保全と相続の円滑な手続きのために、死亡の事実を確認した時点で口座を凍結します。
配偶者の相続を放棄した場合、最初から相続人ではなかったと見なされることから、凍結された口座から預貯金を引き出すことはできません。
葬儀費用のために引き出す場合でも、原則として相続財産に手をつけることはできません。
家に住めなくなる可能性がある
配偶者の死後に相続放棄をすると、家の相続権を失います。
他の相続人が家を相続すると、処遇次第では住む家を失う可能性があります。
家が配偶者の義父母の持ち家の場合、義父母が家を他の相続人へ売却してしまう可能性も想定しておかなければいけません。
相続財産に空き家や山林がある場合
相続財産に空き家や山林がある場合のデメリットとして、以下の3つがあります。
- 相続放棄をしても管理責任を問われる可能性がある
- 処分費用などについてトラブルに発展する可能性がある
- 不法投棄されたゴミの責任を問われる可能性がある
順番に見ていきましょう。
相続放棄をしても管理責任を問われる可能性がある
相続放棄をしても相続財産に空き家や山林など、管理を必要とする不動産が含まれている場合は、相続放棄してもすぐに管理責任から逃れることはできません。
民法940条によって、次の相続人が決まるまで、もしくは相続財産管理人が選任されるまでは、放棄した相続人に管理義務があります。
管理を怠ったことが原因で損害が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
処分費用などについてトラブルに発展する可能性がある
相続財産に空き家や山林がある場合は、処分のための解体費用や伐採費用として、高額な費用が必要となるケースがあります。
相続放棄をすると処分費用を負担する義務はなくなりますが、他の相続人の負担が大きくなるため、親族の間でトラブルに発展することがあります。
円満解決に落とし込むためには、相続放棄をする前に他の相続人と空き家や山林について話し合い、費用負担においても明確にしておかなければいけません。
不法投棄されたゴミの責任を問われる可能性がある
前述のとおり民法940条の管理義務に基づいて、次の相続人や相続財産管理人が決まるまでの間、適切な管理を怠ったと見なされると、損害賠償責任に問われる可能性があります。
空き家や山林への不法投棄が、何かしらの問題を引き起こした場合、管理責任を追求される恐れがあることは十分に認識しておかなければいけません。
事業用資産が相続財産に含まれる場合
事業用資産が相続財産に含まれる場合のデメリットとして、以下の2つがあります。
- 事業継続ができなくなる
- 従業員や取引先からの信頼を損なう可能性がある
順番に見ていきましょう。
事業継続ができなくなる
店舗や工場など、事業資産が相続財産に含まれる場合、相続放棄をすると事業継続が困難になります。
親から引き継いだ店舗で事業を営んでいた場合、相続放棄をすることによって、店舗の所有権を失うことになり、事業を続けるための拠点を失うことになります。
他の相続人に事業を引き継ぐ意思がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合は、事業の継続を諦めなければいけません。
従業員や取引先からの信頼を損なう可能性がある
事業の代表者や経営者が交代することによって、事業継続の不確実性が高まるため、取引先からの信頼を失う可能性があります。
また相続放棄によって、事業に必要とされる工場や店舗、仕入れルートなどがバラバラになり、取引の遅延だけでなく品質の低下を招いてしまうおそれもあります。
健全な取引を継続するには、相続放棄後のスムーズな事業承継は欠かせません。
相続人が高齢者や未成年の場合
相続人が高齢者や未成年の場合のデメリットとして、以下の2つがあります。
- 放棄手続きに家庭裁判所の許可が必要
- 放棄の意思確認が難航することで期限を過ぎるリスク
順番に見ていきましょう。
放棄手続きに家庭裁判所の許可が必要
相続人が高齢者で十分な判断力を有していない、または未成年者のケースでは、本人による相続手続きが難しい場合があります。
相続人が高齢者や未成年の場合は、成年後見人や特別代理人を選任したうえで、家庭裁判所の許可を得て相続手続きを進めなければいけません。
手続きには成年後見人選任の申し立てや、特別代理人選任の申し立てが必要です。
多くの手間や時間、費用がかかることから、相続人が高齢者や未成年の場合は、あらかじめ専門家へ相談しておき、適切な手続きを進めることが大切です。
放棄の意思確認が難航することで期限を過ぎるリスク
相続人が高齢で判断力が低下している場合や未成年の場合は、相続放棄の意思確認ができないことがあります。
意思確認が困難な場合は、成年後見人や特別代理人を選任しなければいけませんが、手続きに時間がかかってしまい、熟慮期間である3ヶ月を超えてしまう可能性もあります。
熟慮期間を過ぎてしまうと相続を承認したと見なされてしまい、負債の相続放棄ができません。
相続放棄のデメリットに関するよくある質問

相続放棄のデメリットに関するよくある質問をまとめました。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
はい、一般的に生命保険金は受取人固有の権利であり、相続財産には含まれません。
受取人として指定されている限り、相続放棄をしていても受け取れるのが原則です。
ただし、保険契約によっては例外もあるため、契約書の内容を確認しておくことが重要です。
相続放棄をした後に家に届いた請求書は無視すべき?
原則として、相続放棄が家庭裁判所に正式に受理された後は、被相続人の債務に対して法的な支払義務はありません。
ただし、請求先の業者が放棄を把握していないこともあるため、相続放棄の申述受理証明書を提示して通知しましょう。
放置せず、書面で対応するのが安全です。
相続放棄したあとに勝手に遺品を整理してしまったらどうなる?
遺品整理や処分行為は「相続を承認した」とみなされる可能性があり、相続放棄が無効と判断されるおそれがあります。
どうしても遺品整理が必要な場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てたうえで対応するのが安全です。
相続放棄の申述が却下されるケースはある?
あります。たとえば申述期限である3か月を過ぎていた場合や、既に遺産の処分をしていた場合などは、相続放棄の申述が却下されることがあります。
そのため、相続放棄を検討し始めたら、早めに専門家に相談することが重要です。
被相続人の借金があるかわからないけど相続放棄するべき?
債務の有無が不明な場合、まずは金融機関や信用情報機関(CIC・JICC)などで借入履歴やローン残高を調査することができます。
熟慮期間である3か月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所へ期間伸長の申し立てをする方法もあります。
| ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 引用元:民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間) |
相続放棄したら、戸籍には記録が残る?
相続放棄の記録は、戸籍には残りません。
ただし、家庭裁判所での記録としては残り、申述受理証明書を取得すれば証明可能です。
相続関係の手続きで証明が必要な場面では、この証明書を使用します。
相続放棄の相談は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターまで
相続放棄をすると、被相続人の負債を負わずに済みますが、同時にプラスの財産まで放棄してしまうことになります。
また、相続に関する全てのことを放棄するため、必要な手続きを進められない場合がある点にも注意が必要です。
相続放棄は申し出が認められた後は、原則として撤回できません。
やり直しは効かないため、事前に十分な精査のうえ、慎重に判断しましょう。
相続放棄の判断について、自分では決断できない場合は専門家へご相談ください。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、各士業の連携によって、それぞれの課題を解決に導きます。
イレギュラーパターンにも柔軟に対応できますので、お悩みの方はぜひご相談ください。
電話でのお問い合わせ





コメント