相続した土地を3年以内に売却することが重要な理由とは?相続税の特例を解説

なぜ相続した土地は3年以内に売却した方が良いのでしょうか。
- 相続税の取得費加算の特例
- 特例の適用条件
- 3年以内に関する税制上の注意点
以上3つのポイントにて詳細を説明します。
相続税の取得費加算の特例
相続税の取得費加算の特例とは、相続や遺贈で得た不動産などを、「相続の事実を知った日から3年後の12月31日まで」に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
取得費加算の特例によって譲渡所得が減り、譲渡所得税を抑えることができます。
特例の適用条件
特例の適用条件は次のとおりです。
- 相続または遺贈によって取得している
- 財産を取得した人が相続税を納税している
- 相続の事実を知った日の翌日から3年後の12月31日までに売却している
以上の条件を満たしつつ確定申告を行うことで特例が適用されます。
特例が適用されると取得費をより多く計上できるため、結果として譲渡所得税を抑えられる仕組みです。
3年以内に関する税制上の注意点
相続税の取得費加算の特例では、確定申告が必須です。
特例を適用し税金がゼロになっても、確定申告をしなければいけません。
申告しないと特例が適用されず、本来不要な税金を請求される可能性があるため申告が必要です。
これは税法上の義務でもあります。
取得費加算の特例と「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」は併用できないため注意が必要です。
どちらの特例を使うべきか、慎重に検討しなければいけません。
遺産分割協議は、特例期限までに完了させる必要があります。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%が取得費と見なされるため、特例を使っても税負担が大きくなる可能性があるため要注意です。
相続した土地を3年以内に売却する場合の注意点

売却の際の注意点は、次の4点です。
- 相続した土地が市街化調整区域にある場合、3年以内の売却をしづらいことがある
- 不動産を売却するうえで発生する税金がある
- 地目変更が必要な相続土地を3年以内に売却することは難しい
- 相続登記が済んでいないと、売却そのものができない
それぞれについて詳しく説明します。
相続した土地が市街化調整区域にある場合、3年以内の売却をしづらいことがある
市街化調整区域の土地の売却は注意が必要です。
市街化調整区域は原則として新たな建物の建築が制限されており、開発行為も厳しく規制されています。
そのため、買主を見つけるのは簡単なことではありません。
売却に時間がかかる傾向があります。
特例の適用期限までに、買い手が見つからないと、せっかくの税制優遇を受けられません。
売却価格も市街化区域の土地に比べて低くなることが多く、希望通りの価格で売却できない可能性もあります。
不動産を売却するうえで発生する税金がある
相続税の取得費加算の特例を使っても、不動産の売却に伴う税金がゼロになるわけではありません。
特例では取得費の加算にとどまるので、譲渡所得が残れば課税されます。
また、不動産の所有期間によって税率が大きく異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期譲渡所得(税率約20%)、5年以下なら短期譲渡所得(税率約39%)となり、短期譲渡所得だと税負担が大幅に増える可能性があります。
所有期間の計算は、被相続人の取得日から引き継がれることをよく覚えておきましょう。
地目変更が必要な相続土地を3年以内に売却することは難しい
地目変更が必要な土地の売却は時間がかかるため、特例適用には難易度が高いです。
「農地」から「宅地」などへの地目変更は、農業委員会の許可や農地転用手続きが必要です。
少なくとも数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
市街化調整区域の農地ではさらに難しく、許可が得られない可能性も考えられます。
特例の期限内にこれらの手続きを終え、買主を見つけ、売買を完了させるのは時間的にかなりタイトになるでしょう。
相続登記が済んでいないと、売却そのものができない
相続税の取得費加算の特例を利用するには、相続登記が完了している必要があります。
被相続人名義のままでは売却できません。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が義務付けられました。
相続登記をせずにそのままにしておくと、罰則のリスクも生じます。
特例の期限を考えると、相続登記の手続きに要する時間を考慮し、余裕を持って進める必要があります。
手続きがよくわからない方は、司法書士に相談して速やかに登記を完了させた方が良いです。
相続した土地を3年以内に売却するまでの5ステップ

不動産を売却するまでの手順は次の5ステップです。
- ステップ1:売却の準備と情報収集
- ステップ2:信頼できる不動産会社を選ぶ
- ステップ3:売却活動のスタート
- ステップ4:売買契約の締結と決済・引き渡し
- ステップ5:売却後の確定申告
それぞれの手順について詳しく説明します。
ステップ1:売却の準備と情報収集
相続した土地を売却する第一歩は、売却の準備と情報収集です。
具体的には、まず境界が不明確でないか、越境物がないかなど現況を確認します。
次に、登記簿謄本、固定資産評価証明書、地積測量図など、必要書類を揃えます。
最後に売却価格の相場調査を行い、土地の適正な価値を把握できたらステップ1は完了です。
最初の準備を早めに行うことで、後の手続きがスムーズになり、特例の期限にも間に合いやすくなります。
ステップ2:信頼できる不動産会社を選ぶ
相続した土地を高値で、かつスムーズに売却するためには、信頼できる不動産会社選びが鍵となります。
査定は複数の不動産会社に依頼します。
チェックポイントは査定額だけではありません。
査定額の根拠を明確に説明してくれるか、地域の土地事情や相続物件の売却実績が豊富かを確認しましょう。
担当者の対応の丁寧さや、売却に向けた販売戦略の提案も見極めたいところです。
一括査定サイトなどを活用して、複数の会社の比較検討をおすすめします。
ステップ3:売却活動のスタート
不動産会社と媒介契約を結ぶと、いよいよ売却活動のスタートです。
不動産会社は、ウェブサイトへの物件情報掲載や広告、オープンハウス開催などを通じて、購入希望者を探します。
売却活動期間は、買主からの問い合わせや内覧の申し込みが入ります。
いつでも内覧に応じられるよう、物件を常にきれいに保つことが大切です。
不動産会社と密に連携を取りながら、売却の成功を目指しましょう。
ステップ4:売買契約の締結と決済・引き渡し
買い手との話がまとまると、売却価格や引き渡し日などの条件を調整し、売買契約を締結します。
買主から手付金を受け取った後は、司法書士に依頼して所有権移転登記の準備を進め、残金を受け取る「決済」へと進みます。
決済日に鍵の引き渡しを行い、不動産を正式に買主に引き渡した時点で売却の完了です。
ステップ5:売却後の確定申告
不動産の売却完了後は、翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に譲渡所得税の申告と納税が必要です。
特例を適用して税金がゼロになる場合でも、必ず申告しなければなりません。
売却でかかった費用や相続税の取得費加算の特例などを活用し、正確な譲渡所得を計算します。
申告を怠ると、追徴課税などのペナルティが科されます。
難しい場合は税理士に相談するなどして、忘れずに手続きを行いましょう。
相続した土地を3年以内に高値で売却するために抑えておきたいポイント

不動産を高値で売却するために抑えておきたいポイントは次の4点です。
- 不動産会社選びと価格設定
- 物件をよりよく見せてのアピール
- 入念な事前準備
- 自分だけでは難しいと感じた場合の、専門家への相談
それぞれについて詳しく説明します。
不動産会社選びと価格設定
不動産を高値で売却するために重要なのは、まず適正な価格設定です。
相場を無視して高く設定してしまうといつまでたっても買い手がつきません。
逆に相場よりも安い価格で売る羽目になることもあります。
複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額の根拠を比較して、適正価格の「ストライクゾーン」を見極めましょう。
信頼できる不動産会社選びも不可欠です。
査定額が高いだけでなく、販売戦略や担当者の対応力、地域に詳しいかなどを総合的に判断します。
複数社を比較検討のうえ、最も信頼できるパートナーを見つけることが、高値売却への第一歩となります。
物件をよりよく見せてのアピール
不動産を高値で売却するには、購入希望者に良い印象を与えなければいけません。
内覧前には、家全体を徹底的に清掃し、整理整頓しましょう。
特に水回り(キッチン、浴室、トイレ)を綺麗にしておくと、印象が良くなります。
内覧する人のイメージをサポートするためにも、余計な家財道具はおかずに生活感を無くした方が良いでしょう。
カーテンを開けて部屋を明るく見せることも効果的です。
簡易なリフォームや修繕で見た目の印象が大きく向上する場合もあるため、不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
入念な事前準備
不動産を高値で売却するには、入念な事前準備が欠かせません。
本格的な売却活動に入る前に、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの必要書類を早めに揃えましょう。
周到な準備によって、売却手続きがスムーズに進みます。
土地の境界線や越境物の有無など、物件の状況を正確に把握しておくことも大切です。
事前準備を怠ると、売却活動中に問題が発覚するなどして、最悪の場合は売買が破談になったりするリスクが高まります。
自分だけでは難しいと感じた場合の、専門家への相談
相続した土地は、税金や法律、登記など専門的な知識が複雑に絡み合います。
自分だけで手に負えないと感じた時は、速やかに税理士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家へ相談しましょう。
専門家の力を借りることで、特例を最大限に活用したり、法的なトラブルを未然に防いだりすることができます。
無理に自分で頑張るよりも専門家へ依頼した方が、結果的に安全かつ有利に売却できるケースも多いです。
相続した土地を3年以内に売却することに関するよくある質問

不動産の売却について、よくある質問を8つピックアップしました。
- 「3年以内」っていつから数えるんですか?
- 3年を過ぎるとどうなりますか?
- 売却益が出ない場合でも3年以内に売る意味はありますか?
- 空き家でない土地でも特例は使えますか?
- 特例を適用した後の譲渡所得税はいくらですか?
- 売却時にかかる諸費用は総額でいくらかかりますか?
- 複数人で相続を進める場合はどうしたらいいですか?
- 古い家屋の解体は必要ですか?
それぞれの質問について、詳しく説明します。
「3年以内」っていつから数えるんですか?
「3年以内」とは、正確には「相続があったことを知った日の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」を指します。
たとえば、相続の事実を知り得た日が2021年5月とすると、3年以内の期限は2024年12月31日ということになります。
満3年ではなく、3年目の12月31日が期限です。
3年を過ぎるとどうなりますか?
3年を過ぎると、相続税の取得費加算の特例は適用できません。
売却益に対する譲渡所得税の負担が増えてしまい、税金面でのメリットが失われてしまいます。
特例の有無で数十万円の差が生じることもあるため、期限を忘れないようにしたいところです。
売却益が出ない場合でも3年以内に売る意味はありますか?
売却益が出ない場合は、特例のメリットはありません。
将来、不動産の価値が下がるリスクや固定資産税の負担を回避する意味では、早めの売却はおすすめできます。
空き家でない土地でも特例は使えますか?
相続税の取得費加算の特例は、相続した不動産全般に適用されるため、空き家でも利用できます。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」とは併用できないので注意が必要です。
特例を適用した後の譲渡所得税はいくらですか?
特例適用後の税額は次のとおりです。
(売却価格 – 取得費 – 譲渡費用 – 特例で加算された相続税額)×税率
税率は所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。
譲渡益が出なければ税金はかかりません。
売却時にかかる諸費用は総額でいくらかかりますか?
不動産売却の諸費用は、売却価格によって大きく変動します。
総額の目安は、売却価格の4%~6%程度です。
主な内訳は、仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)、印紙税、登記費用、測量費などです。
概算ですが、2,000万円の土地なら80万円~120万円ほどかかる可能性があります。
複数人で相続を進める場合はどうしたらいいですか?
複数人で相続する場合は、まず遺産分割協議が必要です。
誰がどの財産を相続するか全員で話し合って決めます。
話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の署名と実印を押印します。
話をまとめないと不動産の売却や相続登記ができません。
古い家屋の解体は必要ですか?
相続税の取得費加算の特例の利用では、家屋の解体は必須ではありません。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を利用する場合は、原則として古い家屋の解体、もしくは耐震改修が必要です。
2つの特例は併用できないため、どちらかを選ぶ必要があります。
相続した土地を3年以内に売却する上で迷っている方は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください

相続した土地を持て余している方は、3年以内の売却がおすすめです。
3年以内の売却では相続税の取得費加算の特例が受けられます。
特例には3年の期限が設けられているため、売りにくい物件など特殊な事情が伴う場合は、早めの準備とスムーズな売却手続きが必要です。
相続した土地の売却に困っている方は、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください。
弊社では、司法書士などさまざまな士業との連携によって、お客さまの課題をワンストップで解決しています。
些細なことでもご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせ


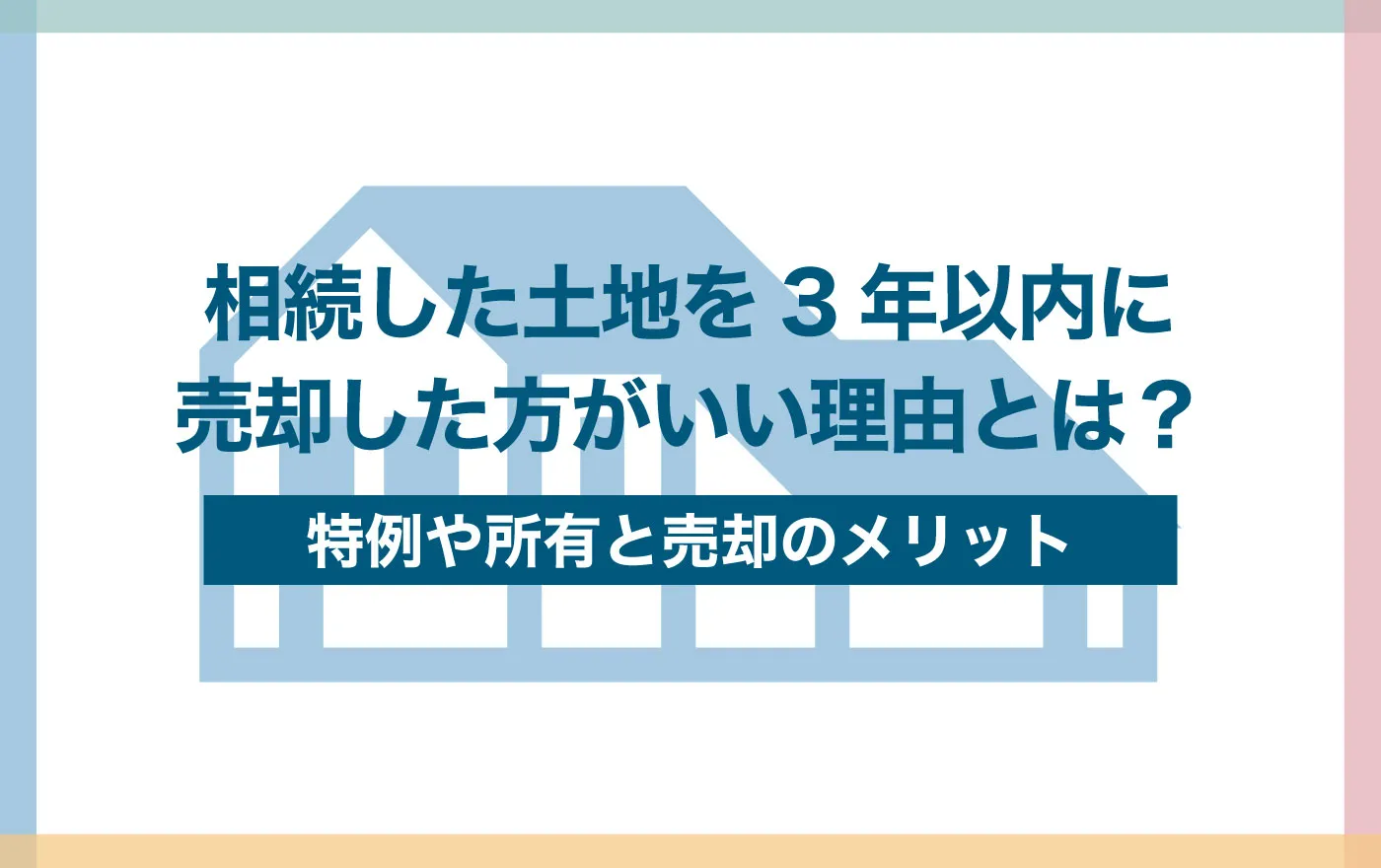


コメント