不動産相続において、弁護士は士業の中で最も多くの項目を対応することができます。
しかし、実際は不動産相続において最初から弁護士に依頼することは少なく、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に、相続税の申告は税理士に、遺産分割において親族間で揉めてしまった場合に弁護士に依頼することが多いです。
なぜなら、遺産分割において発生したトラブルに介在できるのは士業の中でも弁護士だけだからです。
この記事では、不動産相続を弁護士へ依頼すべきシーンや、依頼するメリット、依頼費用の相場などをくわしく解説します。
不動産相続における揉め事に介在できるのは弁護士だけ

不動産相続において、各士業が対応できる項目は次表の通りです。
| 業務 |
弁護士 |
司法書士 |
行政書士 |
税理士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続登記の申請代理(不動産の名義変更) | 〇 | 〇 | × | × |
| 遺産分割の交渉代理(当事者間の代理交渉) | 〇 | × | × | × |
| 遺産分割の調停・審判の代理(家庭裁判所) | 〇 | × | × | × |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | △(※1) |
| 相続放棄申述書など「家庭裁判所」提出書類の作成 | 〇 | 〇(※2) | × | × |
| 相続税の申告・税務相談 | △(※3) | × | × | 〇 |
| 遺言作成サポート(自筆/公正証書の文案・公証役場手配等) | 〇 | 〇 | 〇 | △(※4) |
※1:税理士は税務観点からの助言は可能だが、法的紛争の代理や裁判所手続は不可。
※2:司法書士は「裁判所提出書類の作成」は可(代理人としての出廷・訴訟代理は不可)。
※3:弁護士が税理士資格を併有する場合は相続税申告も可。通常は税務申告は税理士の業務。
※4:税理士は税務面の助言は可。文案作成・手配は対応可否が事務所によって分かれる。
遺産分割の調停・審判の代理(家庭裁判所)や遺産分割の調停・審判の代理(家庭裁判所)など、不動産相続において親族間で揉め事が発生した場合に対応できるのは弁護士だけです。
【大前提】弁護士は依頼した方の味方

弁護士は第三者的かつ中立なイメージがある方が多いと思いますが、大前提として弁護士は依頼した方の味方です。
相続人同士でトラブルが発生した場合に、相続人全員が合意の上で弁護士に依頼した場合は、第三者的かつ中立的な立ち位置で揉め事を解決してくれますが、全員の同意がない場合、弁護士は依頼された相続人の味方となります。
たとえば、揉めている相手が弁護士を雇った場合、「向こうが弁護士を依頼してくれたから、この揉め事も中立的に話がまとまるだろう」と考えるのは大間違いです。
依頼した相続人がスムーズに話を進められるように弁護士は動くので、他の相続人も弁護士に依頼して進めるなどの対応が必要になります。
一方で、相続人の中に厄介な方がいて揉めている場合は、弁護士に依頼することで厄介な交渉の窓口になってくれるだけではなく、その後の調停から審判まで一括して引き受けてくれるため、自身で交渉するよりも心理的な負担が少なく、終局的な解決につながります。
不動産相続を弁護士へ依頼するメリット

不動産相続を弁護士へ依頼する場合、相続人全員が合意して弁護士に依頼した場合と、相続人の一部が全員の合意なしに依頼した場合でメリットが変わってきます。
相続人全員が合意して弁護士に依頼するメリット
不動産相続で相続人同士で揉めていて、「このままでは埒が明かない」「協議がまとまらない」という理由で相続人全員が合意して弁護士に依頼した場合、中立的な立場から法的に妥当な解決策を示し、話し合いをスムーズに進めてもらうことができます。
具体的なメリットは次の3つです。
- 相続手続きが円滑に進む
- 中立的な法的助言を受けられる
- 相続人同士の合意形成をサポートしてもらえる
相続人同士だと私的な感情が出てしまい、話し合いが一向に進まなかったり、冷静に物事を考えられなくなってしまいます。
弁護士という第三者が間に入ることにより、冷静かつ中立的な目線でそれをまとめることができるのが最大のメリットと言えるでしょう。
相続人の一部が全員の合意なしに依頼するメリット
不動産相続で相続人同士が揉めていて、相続人の一部が弁護士に依頼した場合は、依頼者の味方として弁護士は動きます。
この場合の主なメリットは次の4つです。
- 自分の権利をしっかりと主張できる
- 紛争の早期解決ができる
- 法的リスクを軽減できる
- 心理的な負荷が少ない
基本的には弁護士が交渉の窓口となり、揉めている相続人と話を進めてくれるので、法律的に不利になりにくく、かつ紛争の早期解決が期待できます。
また、揉め事に巻き込まれると精神的にも大きな負担がかかります。
中には「言いたいことがあるが、争いの雰囲気に飲まれてしまってなかなか言い出せない」という方もいらっしゃるでしょう。
弁護士が窓口となることで「自分の代わりに自分の意見を主張してくれる味方がいる」という安心感があり、相続人同士の感情的な衝突に一人で立ち向かわずにすみます。
不動産相続で弁護士に依頼を検討すべきタイミング

不動産相続において、弁護士へ依頼を検討すべきタイミングは「揉め事が発生した時」と「揉め事が発生しそうな時」の大きく2つです。
揉め事が発生した時
すでに相続人同士で揉め事が発生してしまった場合には、解決できるのは弁護士しかいません。
次のような場合は、できるだけ早く弁護士に依頼すべきです。
- 相続分や不動産の扱いを巡って話し合いが平行線の状態になっている
- 一部の相続人が強硬に権利を主張している
- 感情的な言い争いになり、相続人同士では冷静な話し合いが困難になっている
このような状況を相続人同士で解決しようとすると、人間関係がさらに悪化し、泥沼化してしまう可能性があります。
「このままでは話がまとまらないので、弁護士を立てて冷静に話合いましょう」と相続人全員が合意の上で弁護士に依頼するのが最も中立的でベストな解決策ですが、それが叶わない場合には相続人の一部で弁護士を立てるのがベターです。
揉め事が発生しそうな時
まだ揉め事にはなっていないものの、将来的に争いに発展する可能性がある場合も、弁護士への相談を検討すべきタイミングです。
次のような段階で弁護士に相談しておけば、争いに発展することなく解決できる場合があります。
- 不動産の分割方法について相続人同士で意見が食い違っている
- 特定の相続人が主導権を握って話を進めており、不公平感が出てきている
- 相続人同士に感情的な溝が生じつつあり、関係が悪化しそうな兆候がある
「このままでは揉め事に発展してしまいそうなので、弁護士を立てて冷静に話し合いましょう」と全員が合意の上で弁護士に依頼することがこちらもベストではありますが、それが叶わない場合には相続人の一部で弁護士を立てるなどを検討しましょう。
不動産相続で弁護士が行う主なサポート

実際に不動産相続で弁護士に依頼した場合に弁護士が提供するサポート内容は主に次の3つです。
- 法律的なアドバイスの提供
- 遺産分割協議のサポート・代理
- 紛争・訴訟対応
相続登記や、相続放棄・限定承認などの相続手続き支援や税務面での相談なども弁護士は対応できますが、不動産相続手続きの支援であれば司法書士、税務面での相談であれば税理士に依頼するのが一般的です。
「揉め事が発生しそう・した時」に弁護士に依頼するのが一般的です。
法律的なアドバイスの提供
不動産相続に関する法律は複雑で、相続人の数や不動産の種類によって手続きも変わります。
たとえば、遺言書が存在しない場合や、遺産分割協議が難航している場合など、依頼に基づき法律的なアドバイスをしてもらえます。
ただし、依頼者が相続人全員である場合には中立的なアドバイスをしてくれますが、依頼者が相続人の一部である場合は依頼者の味方として法律的なアドバイスを提供するという点には注意しましょう。
遺産分割協議のサポート・代理
弁護士は遺産分割協議も法律的な見解でサポート・代理が可能です。
相続人全員で依頼した場合には、遺産分割協議を法律的な見解に基づき解決案などを出してくれますが、相続人の一部が依頼した場合には、依頼者の主張に対して相続人同士の合意が得られるようにアドバイスを行ったり、調整、代理人としての交渉を行ってもらえます。
紛争・訴訟対応
遺産分割協議が難航したり、相続人間での対立が激しくなると、最終的には裁判に発展することもあります。
こういった裁判に関する訴訟手続きや、訴訟中の交渉など裁判に関する一連の対応を依頼者に代わり、代理人として円滑に進めることが可能です。
不動産相続について弁護士に依頼する際に抑えておきたいポイント

不動産相続を弁護士へ依頼する際に、抑えておきたいポイントは次の5点です。
- 事前準備
- 不動産相続の経験の有無と内容
- コミュニケーションの取りやすさ
- 報酬体系の明確さ
- 初回相談無料の有無
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
事前準備
弁護士へ依頼する前に、あらかじめ事前準備をしておくと、その後の手続きもスムーズです。
依頼前に用意しておくと良いものは次のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍や遺言書
- 不動産の登記簿や固定資産税の書類
- 家族の関係図(だれが相続人なのか)
- トラブルになっている内容のメモ
必要書類と経緯のメモや相続関係図などを用意しておくと、弁護士はすぐに必要な手続きに取り掛かることができます。
不動産相続の経験の有無と内容
弁護士を選ぶ際は、不動産相続の経験の有無を確認します。
不動産は評価や分割が複雑な上、相続人間でトラブルになりやすいため、専門知識と解決実績を持つ弁護士の方が、良い結果が得やすいです。
依頼を検討する際は、最初に事務所のサイトで実績を確認しましょう。
初回相談時に具体的な事例について質問すると、経験の有無を推し量ることもできます。
コミュニケーションの取りやすさ
実務とは無関係のように思えますが、コミュニケーションの取りやすさは意外と重要です。
不動産相続は複雑で、デリケートな問題も含まれるため、不安な点や疑問を気軽に質問できる関係性が求められます。
弁護士の話し方や説明の分かりやすさ、レスポンスの速さなどもチェックポイントです。
信頼できる弁護士であれば、精神的な負担を感じることなく、安心して手続きを進められます。
報酬体系の明確さ
報酬体系の明確さは、安心して依頼するために見逃せないポイントです。
相談料、着手金、成功報酬、実費、日当など、費用の種類や算出方法が事前に明確に提示されているか確認しましょう。
後から予期せぬ追加費用が発生しないよう、書面での見積もりを求めることも大切です。
不明点は納得いくまで質問して解消しましょう。
不明点をなくすことで費用の不安を解消できます。
初回相談無料の有無
弁護士へ依頼するときは、初回相談をうまく活用したいところです。
多くの法律事務所では、初回無料相談を実施しています。
初回相談無料があれば、費用を気にせず、複数の弁護士に相続の状況を説明し、専門的なアドバイスを受けることができます。
弁護士の対応や人柄、説明の分かりやすさを直接確認できる点も大きなメリットです。
不動産相続を弁護士へ依頼する際の相場

弁護士へ不動産相続を依頼する際に必要な費用は次のとおりです。
- 法律相談料
- 着手金
- 報酬金
- 実費と日当
それぞれの費用の相場について詳しく説明します。
法律相談料
不動産相続における弁護士の法律相談料の相場は、30分あたり5,000円〜10,000円程度が一般的です。
しかし、初回相談を無料としている法律事務所も多くあります。
最初は無料相談を活用し、相続の状況を伝え、弁護士の対応や説明のわかりやすさ、費用体系などをチェックしましょう。
初回無料相談を活用できれば、複数の事務所の比較検討も容易です。
着手金
不動産相続を弁護士へ依頼する際の着手金は、一般的には20万円〜50万円程度が相場です。
着手金は案件の複雑さや遺産総額によって変動します。
着手金は弁護士が業務に着手する際に支払う費用で、結果の成否にかかわらず返還されません。
遺産分割協議の代理交渉などでは、遺産や経済的利益の額に応じて旧弁護士会報酬基準を参考に算定されることが多く、高額な遺産ほど着手金も高くなる傾向にあります。
報酬金
不動産相続における弁護士の報酬金の相場は、案件を解決に導いた後に、依頼者が得る経済的利益の10%〜16%程度が目安です。
報酬金の相場は、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしていることが多いです。
経済的利益の額が大きくなるほど料率は下がります。
たとえば、1億円の遺産から5,000万円を確保できた場合、その経済的利益に対して報酬金が計算されます。
具体的な金額は、依頼内容や解決内容によって大きく変動するため、契約前に確認が必要です。
実費と日当
主な実費は、戸籍謄本や不動産登記事項証明書の取得費用、郵便切手代、交通費、収入印紙代など、手続きに必要な諸経費のことです。
実費の相場は、必要書類の枚数にもよりますが、おおむね数千円〜数万円程度が相場です。
日当は弁護士が遠方への出張や裁判所出廷などの際に発生する費用のことをいいます。
半日で3万円〜5万円、1日で5万円〜10万円程度が相場です。
不動産相続のお困りごとは静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください

不動産の相続は複雑かつ専門性を要する手続きが必要です。
親族間の揉め事などが絡んでくると、専門的な法律の知識なしでは対処が難しいでしょう。
特に、すでにトラブルが発生している場合には、弁護士へ依頼するのが一般的です。
一方、揉め事もなくスムーズな不動産相続が見込める場合は、司法書士への依頼が一般的。
登記や分割協議の書類作成も専門分野の司法書士ならスムーズに進みます。
静鉄不動産の相続サポートセンターは、相続に関するトラブルやお悩み事を包括的に解決しています。
相続に関する悩み事を抱えている方は、お気軽にご相談ください。
司法書士を始めとした、弁護士など専門士業との連携によって、ワンストップで課題の解決に取り組みます。
電話でのお問い合わせ


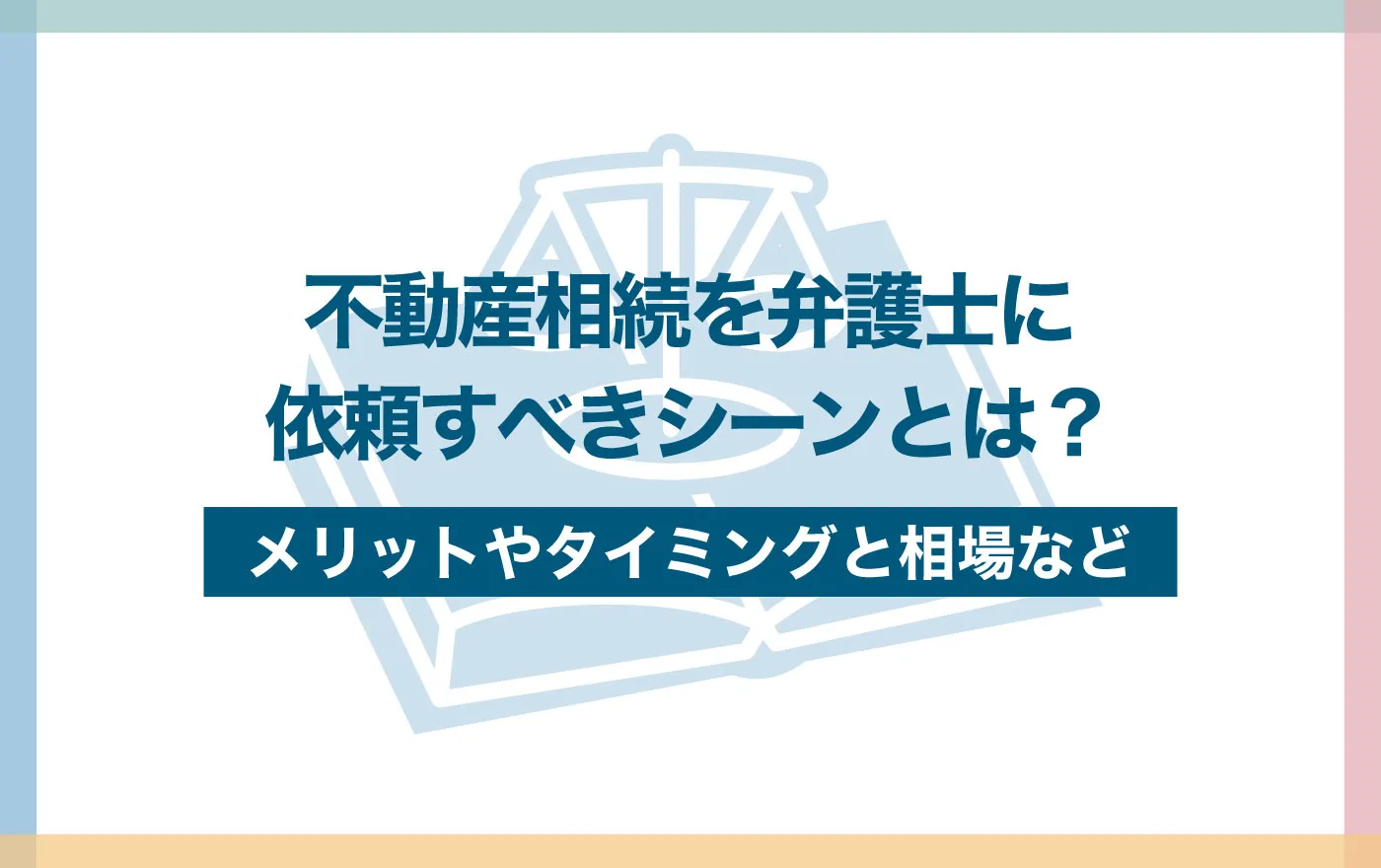
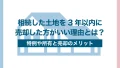

コメント