「亡くなった親の家を相続したら、未登記建物だった!」という事態に陥ったことはありませんか。
こうした状況に直面している方の中には「この家はどうなってしまうのか」「何から手をつけたら良いのかわからない」など、不安と混乱に苛まれている方もおられるのではないでしょうか。
未登記の建物は、複雑さ故に手続きを後回しにしてしまうケースが少なくありません。
しかし、放置すると将来の売却や活用が困難になるだけでなく、子や孫の世代にまで大きな負担を遺すことになります。
この記事では、未登記建物の相続で直面するであろう疑問や不安を解消し、スムーズに手続きを進めるための具体的なステップをわかりやすく解説していきます。
相続における未登記建物はなぜ複雑なのか?

未登記建物の相続はなぜ複雑なのでしょうか。
考えられる要因を3つピックアップしました。
- 法的に整理されていないから
- 登記の手続きが相続時に集中するから
- 相続登記が義務化されたから
それぞれの要因について詳しく説明します。
法的に整理されていないから
未登記建物が複雑な理由の一つに、法的な所有者が明確でないことが挙げられます。
登記簿が存在しないため、誰が所有者なのか、建物がいつ建てられたのかといった情報が公的に証明できません。
未登記建物は遺産分割協議で揉めやすくなったり、将来的な売買や担保設定が困難になったりするなど多くの問題を孕んでいます。
相続において、登記で所有権を明確にすることは必要不可欠です。
登記の手続きが相続時に集中するから
本来、建物が完成した際にすべき登記がされていないと、相続手続きと同時に「建物表題登記」と「相続登記」の両方を行わなければいけません。
未登記建物の存在によって、相続人全員の協力が必要になったり、古い書類の探索や専門家への依頼が一度に重なったりするため、手続きが煩雑になり、手間と費用が増大します。
相続登記が義務化されたから
2024年の法改正により、登記済み不動産については相続登記が義務化されました。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
引用元:民法 | 第76条の2
ただし、相続登記の義務化は「登記済みの不動産」が対象であり、未登記建物そのものには直接は当てはまりません。
しかし、未登記建物を放置しておくと、相続時に「建物表題登記」と「相続登記」を同時に行う必要があるため手続きが複雑化します。
そのため、法的義務の対象ではない場合でも、早めに登記を済ませておくことが重要です。
未登記建物の相続でまず確認したいポイント

未登記建物の相続で確認したいポイントは次のとおりです。
- 本当に未登記なのかを確認する
- 誰が建物を建てたのかを確認する
それぞれのポイントを詳しく説明します。
本当に未登記なのかを確認する
毎年送付される固定資産税の納税通知書は、重要な手がかりとなります。
通常、課税対象となる建物には「家屋番号」が付与されています。
家屋番号が記載されている場合、その建物は少なくとも「表題登記」が完了している可能性が高いです。
家屋番号をもとに、建物所在地を管轄する法務局で「登記事項証明書」を取得できます。
登記事項証明書に建物の情報が記載されていれば、登記が完了していることが確認できるでしょう。
一方で、家屋番号が記載されていない場合は、法務局で「固定資産評価証明書」などを提出し、建物情報を調べてもらう必要があります。
その結果、登記が見つからなければ未登記の可能性が高いといえます。
誰が建物を建てたのかを確認する
原始取得者が誰なのかを確認します。
原始取得者の確認は、相続手続きにおける所有権の証明に不可欠な情報です。
もし被相続人が建物を建てたのであれば、相続人は被相続人から建物を相続したとして手続きを進めることができます。
一方で、もし被相続人のさらに前の世代が建物を建て、そのまま未登記で被相続人が相続していた場合、まず被相続人の親から被相続人へ、そして被相続人から現在の相続人へと、二段階の相続を証明しなければいけません。
建築確認申請書や工事請負契約書などの書類があれば、誰が建てたかを特定する証拠となります。
古い建物では建築に関する書類がないことも多いため、固定資産課税台帳や住民票の除票などを通じて確認します。
原始取得者の確認を怠ると、手続きが複雑化し時間や費用が余計にかかるため、しっかり確認しておきましょう。
未登記建物を相続登記する時の流れ

未登記建物を相続登記する時の流れは次のとおりです。
- ステップ1:建物表題登記
- ステップ2:所有権保存登記・相続登記
手続きごとの詳細を説明します。
ステップ1:建物表題登記
建物表題登記は、まだ登記されていない建物について、所在、種類、構造、床面積など、建物の物理的な現況と所有者を初めて登記簿に記録する手続きです。
建物表題登記によって、建物が公的に存在することを証明できます。
手続きの概要と必要書類
建物表題登記の申請には、建物の所有者であることと、建物の物理的な状況を証明する書類が必要です。
具体的な必要書類は次の4点です。
- 申請書
- 所有者の住民票や印鑑証明書
- 建物の情報を証明するための建物図面・各階平面図
- 建築確認済証や検査済証、工事完了引渡証明書など
建物表題登記の申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。
申請は専門知識が必要になるため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
ステップ2:所有権保存登記・相続登記
建物表題登記が完了し、建物に不動産番号が付与されたら、次に所有権保存登記と相続登記を行います。
所有権保存登記は、建物表題登記後に所有権を初めて登記することを指します。
相続登記は、その所有権を相続によって取得したことを記録するものです。
手続きの概要と必要書類
手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
- 遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)
相続関係を証明する書類一式が必要となります。
また、固定資産税評価証明書も登録免許税算出の際に必要です。
所有権保存登記・相続登記も建物の所在地を管轄する法務局に登記申請書と必要書類一式を提出して申請します。
通常は専門家である司法書士へ依頼するのが一般的です。
未登記建物の相続登記で知っておいたほうが良いこと

未登記建物の相続登記について知っておいた方が良いことを6つピックアップしました。
- 時間と手間がかかる
- 費用がかかる
- 書類収集が難しい場合がある
- 相続放棄と未登記建物の関係性
- 相続登記を放置するとリスクがある
- 専門家に相談すべきタイミング・判断基準
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
時間と手間がかかる
未登記建物の相続登記は、2段階の手続きが必要となるため、通常の手続きよりも時間がかかります。
相続登記の前に、まずは建物の物理的な存在と所有者を公的に証明する、建物表題登記を行う必要があります。
建物表題登記には、古い書類の探索や、土地家屋調査士による現地調査、図面作成などが必要です。
場合によっては数週間から数ヶ月程度の時間がかかる可能性があります。
所有権を相続人へ移転させる所有権保存登記・相続登記ができるようになるのは、建物表題登記が完了し、登記簿が作成されてからです。
所有権保存登記・相続登記の手続きも、相続関係を証明する戸籍謄本などの収集や、遺産分割協議の調整などのために、ある程度の時間がかかります。
費用がかかる
未登記建物の相続登記には、先述の建物表題登記が必要になるため、余計に費用がかかります。
建物表題登記は専門性が高いことから、専門家である土地家屋調査士に現地調査や図面作成を依頼するのが一般的です。
費用は建物の規模や形状によって異なりますが、一般的に数十万円程度かかります。
他には、所有権の移転を登記する所有権保存登記・相続登記のために、司法書士への報酬が発生します。
また、登記の際の登録免許税も必要です。
書類収集が難しい場合がある
未登記建物が古い場合、必要な書類の収集が難しいケースがあります。
建物の物理的な情報を登記する建物表題登記に必要な、建築確認済証や検査済証、工事請負契約書がないパターンはよくあるケースです。
以上の書類がない場合は、固定資産税の納税通知書や近隣住民の証明書など、代替書類を探し出して法務局に個別に相談しなければいけません。
相続放棄と未登記建物の関係性
未登記建物を相続放棄した場合、その物件は次の順位の相続人に引き継がれます。
もし誰も相続人がいない場合、最終的には相続財産管理人が選任され、未登記建物を含む遺産全体が管理・処分されます。
相続放棄をしても、次の相続人が見つかるまで管理義務が残る可能性がある点には要注意です。
安易な放置は、近隣トラブルや損害賠償問題に発展するリスクがあります。
相続登記を放置するとリスクがある
相続登記を放置すると法的な権利者を第三者へ立証することができないため、売却や担保設定が困難になります。
いざ建物を売ろうと思っても、登記が完了していないため買主が見つかりにくく、手続きも大幅に遅れがちです。
また、未登記のまま次の相続が発生すると権利関係がさらに複雑化します。
相続人の一人である親が亡くなった場合、その子である孫たちも新たな相続人になります。
世代を超えることで権利者が増えていき、時間が経過するほど全員の合意形成は難しくなるでしょう。
専門家に相談すべきタイミング・判断基準
未登記建物の存在を把握した時点で「何から手をつけたら良いのかわからない」と感じたら、専門家への相談を検討した方が良いでしょう。
未登記建物は、通常の相続とは異なる複雑な手続きが必要となるため、自己判断で進めるとかえって事態を悪化させてしまいます。
特に、相続人同士の意見がまとまらない場合や、古い書類が全く見つからない場合、法律的な知識が必要な局面では、早急に相談すべきです。
具体的な相談先は、建物の物理的な登記手続きを専門とする土地家屋調査士、相続登記や遺産分割協議書の作成を専門とする司法書士です。
また、相続人同士の紛争がある場合は弁護士への相談を検討します。
未登記建物の相続でよくあるトラブル

未登記建物の相続について、よくあるトラブル事例を2つ紹介します。
- 共有名義人の死亡
- 境界線の紛争や隣地トラブル
トラブル事例について詳しく説明します。
共有名義人の死亡
未登記建物は、複数の相続人の共有名義になっているケースが少なくありません。
共有名義の状態で登記をせずに放置していると、共有名義人の一人が亡くなった際、その持分がさらに次の相続人に細かく分かれてしまいます。
時間の経過によって複雑化した権利関係の元では、円滑な合意形成はかなり難しいです。
建物の売却と改修において、大きな障害となるでしょう。
未登記建物の共有名義人の死亡は、将来の売却や活用の妨げとなるだけでなく、子や孫の世代にまで大きな負担を遺す原因となります。
境界線の紛争や隣地トラブル
登記されていない建物は、土地の登記情報と建物の情報が一致しないことが多く、建物の正確な位置や敷地の境界線が不明確なまま放置されているケースが多いです。
相続の発生後、いざ建物の売却や取り壊しを進めようとした時に、隣接する土地の所有者との間で、境界線の認識に食い違いが生じ、紛争に発展することがあります。
特に古い建物の場合、塀や擁壁が境界線と認識されていたとしても、測量するとずれているケースがよくあります。
境界線トラブルを避けるには、相続時に土地家屋調査士に依頼して正確な測量を行い、境界線を確定させておきましょう。
未登記建物の相続でよくある質問

未登記建物の相続についてよくある質問を4つピックアップしました。
- 未登記でも固定資産税はかかりますか?
- 未登記建物の売却は可能ですか?
- 未登記建物を担保にしてお金を借りられますか?
- 他の相続人が協力してくれない場合はどうしたらいいですか?
それぞれの質問について詳しく説明します。
未登記でも固定資産税はかかりますか?
未登記であっても、固定資産税はかかります。
固定資産税は、登記の有無にかかわらず、市町村が管理する固定資産課税台帳に登録されている建物に対して課税されます。
根拠となっている法律は以下の通りです。
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
引用元:民法 | 第343条
市町村の職員による現地調査の結果、建物の存在が確認されれば、建物の所有者と判断された人物(相続人など)に納税義務が発生します。
未登記だからと言って、税金の支払い義務が免除されることはありません。
未登記建物の売却は可能ですか?
未登記建物の売却は、事実上難しいと言わざるを得ません。
法的な所有者が明確でないため、買主は所有権を取得したことの証明ができず、安心して取引ができないためです。
多くの買主は、所有権が法的に確定していない物件の購入を避けます。
また、金融機関も未登記建物を担保として評価しないため、住宅ローンを利用できません。
未登記建物を売却するには、まず建物表題登記と所有権保存登記を完了させ、所有権を明確にすることが必要です。
未登記建物を担保にしてお金を借りられますか?
未登記建物を担保にお金を借りることは、原則としてできません。
金融機関は不動産を担保として融資する際に、その不動産に抵当権を設定します。
しかし、登記されていない建物は、公的に所有権が証明されていないため、抵当権を設定することができません。
未登記建物は担保としての価値が認められず、融資の対象とならないのが一般的です。
未登記建物を担保に融資を受けたい場合は、事前に建物表題登記と所有権保存登記を完了させる必要があります。
他の相続人が協力してくれない場合はどうしたらいいですか?
他の相続人が協力的でない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法を検討します。
遺産分割調停は、調停委員が当事者間の話し合いを仲介し、合意形成を目指す手続きです。
調停でも解決しない場合は、遺産分割審判に移行した後に裁判官が判断を下すことになります。
建物表題登記を単独の相続人から申請できる場合がありますが、所有権保存登記は原則として全員の協力が必要なため、いずれにしろ話し合いや法的な手続きは必要です。
未登記建物の相続にお悩みの方は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください

未登記建物の放置は、新たな法改正によって、法的に責任を問われるようになりました。
多少の手間はかかるものの、早めに対処しておけば相続登記に漕ぎ着けるのも難しくありません。
しかし、数世代に渡って放置され続けてきた未登記建物を相続登記するのは大変です。
相続人が多い場合や共有名義となっている場合は、より困難を極めるでしょう。
相続登記がされていないと、処分さえできません。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターは、それぞれの士業との連携によって、お客さまの課題をワンストップで解決しています。
複雑な未登記建物の登記に悩まされている方は、ぜひ一度ご相談ください。
数多くの事例から、最善と思える解決策を提案させていただきます。
電話でのお問い合わせ


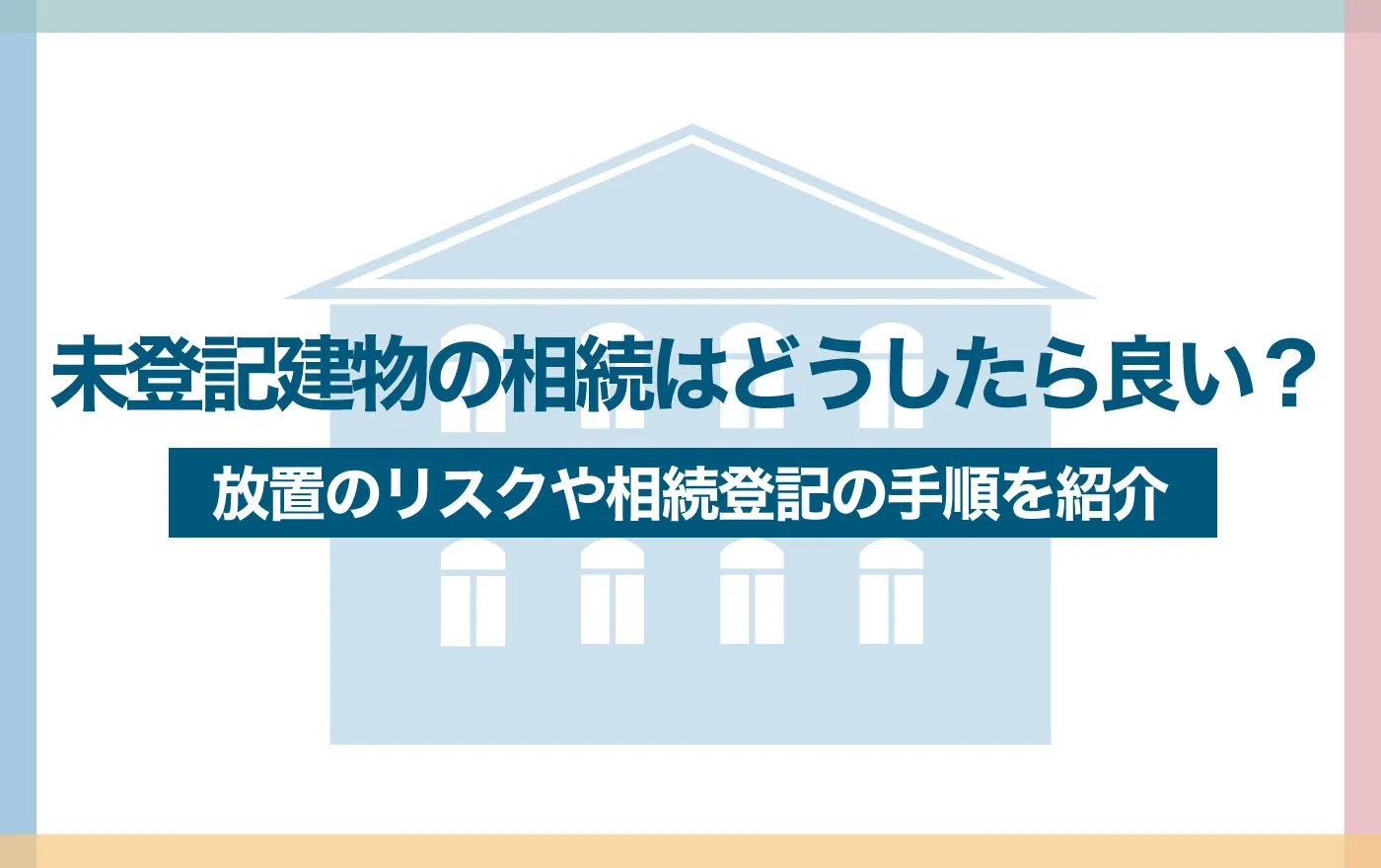


コメント