「相続した土地を現金化して公平に分割したいものの、どうしたら公平な分割ができるのかよくわからない」土地の相続において、このような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
土地や不動産は物理的に分割できないため、公平な相続を考える上で悩みどころでもあります。
具体的には、ビルなど一つの建物を公平に分割するのは現実的に不可能と言っても良いでしょう。
土地を現金化して分割する場合の選択肢は、基本的に換価分割と代償分割、現物分割の3つです。
この記事では、土地を現金化して分割する方法や、評価額の算出方法、注意点などを詳しく説明しています。
相続した土地や現金の分け方3つ!メリット・デメリットも解説

相続した土地を現金にして分割する方法は次の3つです。
- 換価分割
- 代償分割
- 現物分割
それぞれの分割方法について詳しく説明します。
換価分割
換価分割とは相続した不動産や株式などを売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う遺産分割方法です。
分割しにくい財産を公平に分ける際に用いられます。
メリット
換価分割の最大のメリットは、公平な遺産分割が実現しやすい点にあります。
不動産など分割が難しい財産を現金化することで、1円単位で正確に分配できるようになり、相続人間での評価を巡る争いを回避できるようになります。
また、相続税の納税資金を確保できるため、手元に現金がない場合の納税にも対応可能です。
換価分割は相続トラブルのリスクを大幅に軽減し、円満な相続に繋げることができます。
デメリット
売却するために思い入れのある実家や土地を手放さざるを得ない点が挙げられます。
また、売却には不動産会社の仲介手数料や印紙税、測量費などの諸経費がかかるため手取り額が減少します。
売却益が出れば譲渡所得税によって、税負担が増える(例外的に、取得加算税の特例によって勢負担が軽減できることもあります)ことも考慮しておかなければいけません。
不動産の売却には通常、3ヶ月から1年程度の時間がかかることも要注意ポイントです。
売却には相続人全員の協力が必要なため、意見の対立があると手続きが滞る可能性もあります。
手続きの流れ
換価分割を進めるには、遺産分割協議で土地売却による換価分割の旨を合意のうえ、遺産分割協議書を作成しなければいけません。
次に、被相続人名義の土地を相続人の名義へ変更する「相続登記」を行います。
その後、不動産会社を選定して土地の売却活動を進め、買主と売買契約を締結します。
最終的に売却代金を受け取り、そこから諸経費を差し引いた残額を、遺産分割協議書に定められた割合で相続人全員に分配して完了です。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物財産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して、相続分に応じた現金を支払うことで、公平に遺産を分ける方法です。
メリット
代償分割の大きなメリットは、不動産などの現物財産を売却することなく残せることにあります。
先祖代々受け継いできた土地や、事業で使用している不動産などを維持したい場合は代償分割が有効です。
特定の相続人が実家を相続して住み続けたい場合も、代償分割が適しています。
その他には、公平な遺産分割が実現しやすい点もメリットです。
分割が難しい現物財産についても、代償金を支払うことで各相続人の相続分を調整し、金銭的に公平な分配ができます。
デメリット
代償分割は、代償金を支払う相続人に相当の資金力が必要です。
不動産は高額なことが多く代償金も多額になるため、手元に十分な現金がない場合はローンを組むなどの金銭的な負担が生じます。
土地の評価額を巡って、相続人同士でトラブルになりやすい点もデメリットです。
代償金の算出には土地の評価が必要ですが、評価方法によって評価額が大きく変わります。
取得したい側は低く、代償金を受け取りたい側は高く評価したい、という思惑の対立が生じる可能性は認識しておいた方が良いでしょう。
手続きの流れ
代償分割では相続人全員で遺産分割協議を行い、特定の相続人が現物財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うことの合意が必要です。
遺産分割協議の際に、土地などの評価額や代償金の金額、支払い方法、期限などを明確に定めます。
話がまとまったら合意内容を記載した遺産分割協議書を作成し、署名・捺印します。
最終的には、代償金を受け取る相続人へ決められた期日までに代償金を支払い、必要に応じて不動産の相続登記を行って完了です。
現物分割
現物分割とは、土地、建物、預貯金などの相続財産を、そのままの形で各相続人に分配する分割方法です。例えば「土地は長男に、預金は長女に」といった分け方や、土地を分筆して複数人で分ける場合も現物分割です。
メリット
現物分割は、手続きが比較的シンプルで手間がかかりません。
換価分割や代償分割とは異なり、名義変更などの手続きのみで済むことが多く、費用も抑えられます。
現物分割は相続人が希望する財産をそのまま受け取れるため、故人の思い出の品や事業用資産を維持することも可能です。
相続人間での感情的な対立を避けられる点も大きなメリットの一つです。
デメリット
現物分割は、不公平な分割になりやすい傾向があります。
各財産の評価額が異なるため、相続人それぞれに同等の価値の財産を割り振れないケースが多いです。
結果的に価値の高い財産を受け取った相続人と、そうでない相続人との間で不満が生じてしまいます。
また、土地を分筆して分割する場合、分筆によって土地の価値が下がったり、建築基準を満たせなくなったりするリスクがあります。
物理的に分割が難しい建物など、現物分割ができない財産があることも考慮しておきたいポイントです。
手続きの流れ
まず相続人全員で遺産分割協議を行い、どの相続人がどの財産を相続するか具体的に決定します。
話がまとまったら、現物分割の合意内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
その後、遺産分割協議書に基づき、不動産であれば相続登記、預貯金であれば金融機関での名義変更や払い戻し手続きなど、各財産に応じた名義変更手続きを行って手続きは完了です。
相続した土地を現金で公平な分け方をするうえでの評価額算出方法

相続した土地を現金で分割する際の、評価額算出方法は次の3つです。
- 相続税評価額で算出する
- 時価で算出する
- 相続人の主観的評価を考慮して算出する
それぞれの算出方法について、詳しく説明します。
相続税評価額で算出する
相続税評価額は、相続税や贈与税を計算するために国税庁が定めた土地の評価基準です。
主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
路線価方式は、道路ごとに定められた1平方メートルあたりの「路線価」に補正率を掛けて算出します。
路線価は、毎年7月頃に国税庁のウェブサイトで公開される路線価図で確認できます。
倍率方式は、路線価が設定されていない地域で用いられる方法です。
固定資産税評価額に地域ごとの「評価倍率」を掛けて算出します。
評価倍率は国税庁のウェブサイトで確認可能です。
相続税評価額は、実際の市場価格の80%程度で設定されていることが多いです。
公平な算出のポイント
公平な算出には、客観性と正確性の確保が大切です。
路線価や固定資産税評価額といった公的な評価基準に基づき算出し、その計算根拠を明確にします。
評価の客観性を保つことができれば、相続人全員の納得感を得ることができます。
土地の形状や利用状況に応じた各種補正を適切に適用することも忘れてはいけません。
補正により、画一的な評価では見落とされがちな土地の状況が考慮され、より実態に近い評価額となります。
時価で算出する
土地の時価とは、市場で実際に取引される可能性がある価格のことをいいます。
主な算出方法は次の3点です。
- 不動産鑑定士による鑑定評価
- 不動産会社の査定
- 公的価格からの逆算
不動産鑑定士による鑑定評価では、土地の個別的な要因や、周辺の取引事例、収益性などを多角的に分析し、最も客観的で信頼性の高い時価を算出します。
不動産会社の査定では、類似物件の成約事例や現在の売り出し状況、市場の動向などを基に査定額が算出されます。
公示価格からの逆算は、公示価格や相続税評価額、固定資産税評価額などを参考に、市場価格との乖離率を考慮して概算を算出する方法です。
公示価格からの逆算はあくまでも目安であり、実際の取引価格と異なるケースがあります。
公平な算出のポイント
時価での算出においても、ポイントとなるのは客観性と透明性の確保です。
相続人全員が納得できる信頼性の高い評価方法を算出しなければいけません。
最も客観性が高いのは、国家資格を持つ不動産鑑定士による鑑定評価です。
複数の情報源を参考にするのも忘れてはいけません。
不動産会社の査定も参考になりますが、会社によって査定額にばらつきがあるため、複数社に依頼して比較検討すると良いでしょう。
相続人の主観的評価を考慮して算出する
相続税評価額や時価を参考にした算出方法の他には、相続人それぞれがもつ主観的な評価額を参考にする方法もあります。
相続人によって、不動産に対する思い入れや重要度が異なるため、それぞれの感情的な価値を慮る(おもんばかる)ことも大切です。
不動産に対する思い入れを無視して一般的な事例通りの金額で処理しようとすると、不満や対立が起きる可能性が高まります。
公平な算出のポイント
主観的評価を考慮するうえでは、関係者全員の納得を得るための感情への理解と対話による合意形成が必要です。
不動産鑑定士による第三者評価をベースに、主観的な評価を加味します。
最終的には、心理的な納得感で話をまとめることを目指します。
相続した土地を現金で分けるための評価方法を選ぶ際の注意ポイント

円満な相続のポイントは、相続人全員の完全な合意を得る事に尽きます。
法律で決められているわけではないため、どの評価額を採用するかで揉めるケースは多いです。
特に、換価分割や代償分割のように金銭のやり取りが発生する場合、評価額が直接、各相続人の受取額に影響するため、公平性が強く求められます。
相続税評価額は税金計算には使えますが、実際の市場価格とは異なるため、代償分割などでは不公平感が生じやすいです。
一方、時価は客観性が高いですが、費用がかかります。
いずれの方法を選ぶにしても忘れてはいけないのが、評価方法と根拠を明確にし、事前に相続人全員で十分に話し合う事です。
納得したうえで合意形成を図ることができれば、無用な揉め事のリスクを抑えることができます。
相続した土地の現金での分け方で揉める前にできる法的・実務的手段

相続した土地を現金で分ける際に有効な法的・実務的手段は次のとおりです。
- 生前対策
- 遺産分割協議
- 専門家への依頼
それぞれの手段について詳しく説明します。
生前対策
生前対策は、相続発生後のトラブルや手続きの負担を軽減するために有効です。
主な生前対策として、次の3点が挙げられます。
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 家族信託の活用
遺言書は、あらかじめ自分の意思を明確にしておくことで、相続発生時のトラブルを未然に防ぎます。
換価分割や代償分割など分割方法が指定されていれば、相続発生後の話し合いもスムーズです。
生前贈与は、生前に現金や他の財産を贈与することを言います。
前もって贈与しておくことで、相続財産全体のバランスを調整し、土地に偏りがちな相続財産を現金化しやすい状況に整理できます。
年間110万円までの非課税枠を活用した暦年贈与や、特定の目的に対する贈与特例の利用がポイントです。
よく利用される暦年贈与には、教育資金贈与や住宅取得資金の贈与があります。
家族信託は、土地の所有者が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる制度です。
家族信託を利用すると、所有者が認知症などで判断能力を失った後も、現金化して分割する際の障害を取り除くことができます。
遺産分割協議
遺産分割協議では、被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合います。
相続した土地を現金で分割する際には、換価分割や代償分割といった具体的な方法を決定する重要な場となります。
円満な相続を目指すには、全員の合意が大切です。
合意形成できれば、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
合意内容は、後の証拠となるように遺産分割協議書として書面に残しておきます。
専門家への依頼
土地や不動産の相続に強い専門家は次のとおりです。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 不動産鑑定士
専門家と依頼のタイミングについて詳しく説明します。
弁護士
弁護士は、相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。
法的な観点から公平な分割案を提案したり、相続人の主張を法的に裏付けて交渉を進める立場です。
感情的になりがちな話し合いの場で、冷静かつ客観的な視点を提供し、合意形成をサポートします。
弁護士へ依頼を検討するタイミングは次のとおりです。
- 相続人同士の意見が対立し、自力での解決が困難な場合
- 特定の相続人が遺産を独占しようとしている、あるいは話し合いに応じない場合
- 遺言書の内容に疑問がある場合
- 他の相続人から不当な要求を受けていると感じる場合
トラブルが深刻化する前に、無理せず相談するのがポイントです。
税理士
税理士は、相続財産の正確な評価を行い、相続税の計算と申告書の作成を代行します。
相続税は計算方法が複雑です。
土地の評価一つとっても、評価方法によって税額が大きく変わる場合があります。
税理士は小規模宅地等の特例や配偶者控除など、適用可能な税制優遇措置を最大限に活用し、適法な範囲で相続税の負担を軽減するアドバイスを提供します。
税理士へ依頼を検討するタイミングは次のとおりです。
- 遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える可能性がある場合
- 土地や非上場株式など、評価が難しい財産が含まれている場合
- 相続税の特例を適用したいが、手続きが複雑で分からない場合
- 節税対策について具体的なアドバイスを受けたい場合
相続税は申告漏れや計算間違いがあると追徴課税の対象になります。
自分での対処が難しいと感じたら、無理せずに専門家である税理士へ依頼しましょう。
司法書士
司法書士は不動産の相続登記の専門家です。
相続した土地を現金で分割する際、換価分割するにしても、代償分割にしても、一度は被相続人から相続人への名義変更が必要となります。
司法書士は必要書類の収集、遺産分割協議書の作成支援、法務局への申請まで一貫してサポートしてくれる心強い存在です。
司法書士へ依頼を検討するタイミングは次のとおりです。
- 相続財産に不動産が含まれている場合
- 相続登記の手続きが複雑で、自分で行うのが難しいと感じる場合
- 遺産分割協議の内容を法的な遺産分割協議書として残したい場合
- 相続放棄を検討している場合
- 期限内に相続登記の手続きを完了させたい場合
義務化された相続登記の期限を守るためにも、早めに司法書士への相談を検討することをおすすめします。
不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の適正な経済的価値を客観的に評価する専門家です。
相続した土地を現金で分割する際、特に代償分割においては、土地の評価額が代償金の額に直結するため、公平な評価が求められます。
不動産鑑定士は、周辺の取引事例、収益性、土地の形状、立地条件など、多岐にわたる要素を分析し、客観的な根拠に基づいた鑑定評価書を作成します。
不動産鑑定士に依頼を検討するタイミングは次のとおりです。
- 代償分割における土地の評価額を巡って、相続人同士の意見が対立している場合
- 相続財産に、不整形地、広大地、借地権など評価が難しい特殊な土地が含まれている場合
- 相続税の申告で、土地の評価の根拠を明確にしたい場合
- 相続人間の公平性を重視し、誰からも異論が出ないような客観的な土地の評価額を知りたい場合
不動産の評価は専門的な知識が必要です。
相続で揉める原因になりそうな不動産があれば、早めに不動産鑑定士へ依頼した方が良いでしょう。
相続した土地の現金での分け方についてよくある質問

相続した土地を現金で分割する際によくある質問を4つピックアップしました。
- 相続した土地を売却して、売却代金を相続人全員で分けることはできますか?
- 特定の相続人が土地を相続し、その代わりに他の相続人に現金を渡すことはできますか?
- 相続した土地を共有名義にするとどのようなトラブルが発生しますか?
- 複数の相続人の間で話がまとまらない場合はどうしたら良いですか?
それぞれの質問について詳しく回答します。
相続した土地を売却して、売却代金を相続人全員で分けることはできますか?
換価分割を使えば、売却代金を相続人で分割できます。
換価分割では遺産分割協議で土地を売却して現金で分けることに合意した後に、不動産会社を通じて土地を売却します。
諸経費を差し引いた売却代金をみんなで分割する方法です。
特定の相続人が土地を相続し、その代わりに他の相続人に現金を渡すことはできますか?
代償分割という方法によって実現可能です。
代償分割では、1人の相続人が土地や不動産を取得する代わりに、相当の評価額を他の相続人へ分配します。
公平性を確保できる方法ですが、ある程度まとまった資金を用意しなければいけません。
相続した土地を共有名義にするとどのようなトラブルが発生しますか?
安易に土地を共有名義にしてしまうと、後々トラブルの元となりかねません。
過去の事例から、想定されるトラブルを3つピックアップしました。
- 土地に関する重要な意思決定をする際に、共有者全員の同意が必要となる
- 固定資産税や維持管理費などの負担割合で揉める可能性がある
- 持ち分が次の相続人に引き継がれ、共有者が雪だるま式に増えていく
事情によって共有名義を選択せざるを得ない場合は、想定されるトラブルをあらかじめ認識しておきましょう。
複数の相続人の間で話がまとまらない場合はどうしたら良いですか?
遺産分割協議で話がまとまらない場合は、段階的に解決を目指します。
一般的な段階は次の3つです。
- 弁護士への相談
- 遺産分割調停の申し立て
- 遺産分割審判への移行
まずは円満解決のために、弁護士へ仲介を依頼します。
弁護士による交渉でも合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員が仲介に入って、最適な解決策をアドバイスしてくれる制度です。
調停で合意に至らなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」へ移行します。
最後は裁判所の判断によって遺産分割が決定されます。
相続した土地の現金での分け方に迷っている方は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください

相続人が多い場合、土地の分割は簡単ではありません。
相続人それぞれの思いが交錯するため、合意形成ができずに泥沼化する可能性もあります。
相続した土地を現金化して分割するには、換価分割や代償分割、現物分割がありますが、評価額や売却額などを巡って争いに発展するケースも多いです。
公平な土地の相続手続きが難しいと感じたら、無理せずに専門家への依頼をおすすめします。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、相続に特化したワンストップサポートでお客さまの課題を解決しています。
窓口が一元化されるため、手続きに奔走する必要がありません。
長年の実績とノウハウに裏付けされた、迅速丁寧な解決とサポートを心がけております。
相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ


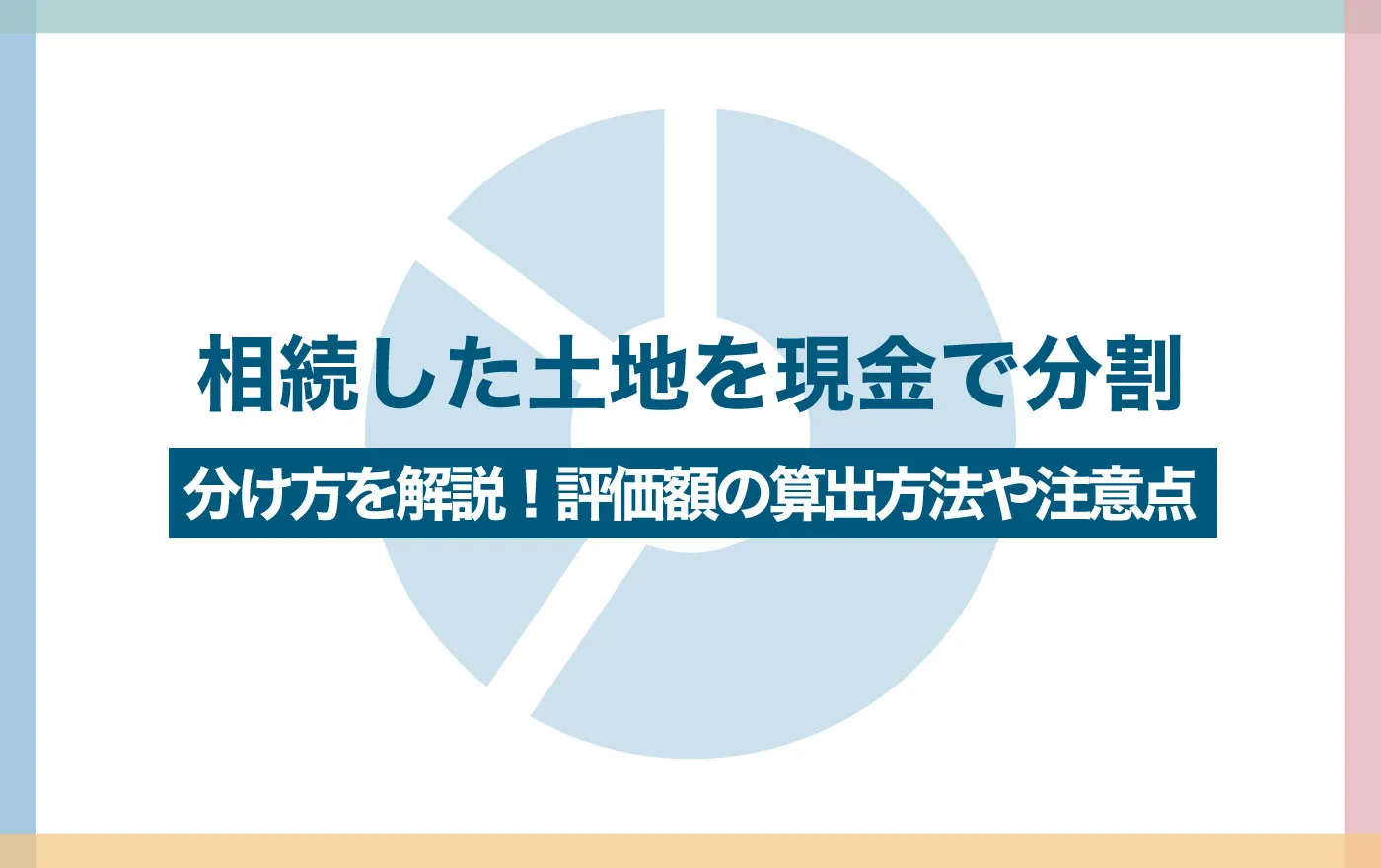


コメント