相続で財産を引き継いだ際に、多くの方が悩むのが不動産に関する取り扱いです。
不動産は評価や税務処理、申告に複雑な部分が多いため、手続きに手間や時間がかかります。
また、申告を誤ると二度手間になるだけでなく、税負担が増加するというリスクも。
この記事では、税理士に相談するメリットや注意点をわかりやすく解説します。
不動産相続を税理士に依頼するメリット

不動産相続を税理士に依頼するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 正確に相続税の申告ができる
- 節税につながる特例などのアドバイスを受けられる
- 税務署での手続代行など進行がスムーズになる
- 二次相続などの相談ができる
- 生前対策ができる
ここからは、それぞれについて詳しくみていきましょう。
正確に相続税の申告ができる
相続税の申告は、不動産評価額をもとに行います。
根拠にした評価額自体が誤っていると過少申告や過大申告になってしまい、追加の手続きに時間や手間を要することに。
税理士に依頼すれば、最新の税制や評価基準に基づいて正確な申告が行えるため、安心して手続きを進められます。
必要書類の収集や書類作成、記載内容のチェックも代行してもらえるので、時間や手間を大幅に節約できるのもメリットといえるでしょう。
節税につながる特例などのアドバイスを受けられる
不動産相続では「どのような土地を」「誰が相続するか」によって、利用できる制度や特例が大きく異なります。
不動産は財産のなかでも価値が高いものが多く、制度や特例を利用できるかによって税額が大きく変わることも珍しくありません。
しかし特例や制度を利用する要件には複雑なものも多いため、専門知識を持つ税理士の判断を仰ぐのがベストです。
相続人や財産の状況、今後の不動産活用など、それぞれの事情に合わせた節税対策についてサポートしてもらうことで、税負担や手続きを軽減する効果が期待できます。
税務署での手続代行など進行がスムーズになる
税理士からは税務署からの問い合わせへの返答や、いつ申告を行えば良いかなどのタイミング調整などのアドバイスが受けられます。
相続登記に必要な書類収集や整理に、各種手続のスケジュール管理にも対応してくれるので、相続登記がスムーズに進められます。
平日は仕事で動けないという方や、相続する不動産が複数ある場合などは、特に大きなメリットになるでしょう。
二次相続などの相談ができる
二次相続とは、一次相続で相続人になった配偶者が亡くなった際に発生する二度目の相続のことです。
一例を挙げると、父親が亡くなって母親と子どもが相続人になるのが一次相続で、その後に母親が亡くなった際に発生するのが二次相続です。
この場合で相続人になるのは子どもですが、一時相続時に適用できた「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」が使えなくなるため、課税対象となる財産の割合が増え、結果として相続税の負担が大きくなる可能性があります。
これから発生するであろう相続も見越したうえで相続対策を行うなら、専門家評価誤差による長期的な計画が欠かせません。
今後のリスクを考慮した財産の分割方法や、生前贈与の活用法など家族構成や財産の状況に合わせたサポートを受けられるのは大きなメリットといえるでしょう。
生前対策ができる
亡くなったあと、遺された人たちに迷惑をかけないよう生前対策を考える方は少なくありません。
税理士に相談することで生前贈与や不動産信託といった、相続対策にも早めに取り組むことができるでしょう。
特に不動産は、相続トラブルの原因になりやすいという側面もあります。
不動産の権利を特定の相続人に譲渡してトラブルを未然に防いだり、年間110万円まで非課税となる暦年課税制度を活用して、数年にわたり贈与を分散させることで、贈与税の負担を抑えながら資産を移転する計画も立てられます。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
不動産相続を税理士に依頼するデメリット
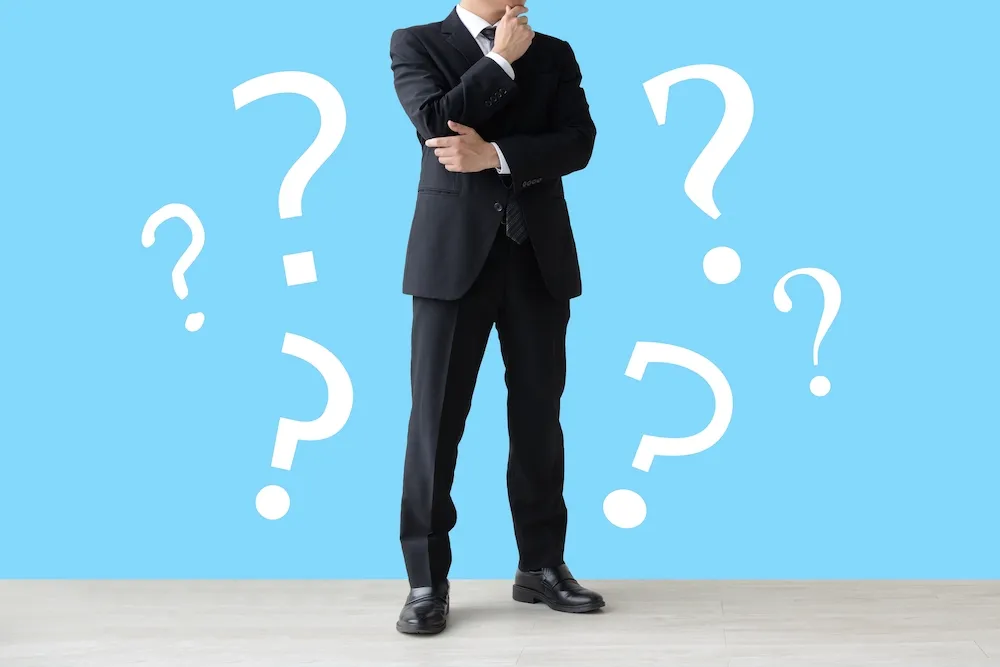
不動産相続を税理士に依頼するには、次のようなデメリットも把握しておく必要があります。
- 税理士報酬がかかる
- 税理士によって得意分野やスキルが異なる
ここからは、それぞれについて詳しくみていきましょう。
税理士報酬がかかる
税理士への依頼には、報酬を支払う必要があります。
報酬の相場は相続財産の額に応じて変動しますが、複雑な案件ほど高額になる傾向があります。
節税効果や時間と手間を節約するという意味では、結果的にプラスになるという考え方もできますが、まずは事前に見積もりを取って費用感を掴むのも大切です。
どういったサポートをしてもらえるのか、費用はいくらかかるのかをしっかり把握したうえで依頼しましょう。
税理士によって得意分野やスキルが異なる
税理士にはそれぞれ得意分野があり、すべての税理士が不動産相続を得意としているわけではありません。
不動産相続は土地や建物の評価、適用できる特例や制度など高度な専門知識が求められます。
実務経験の浅い税理士に依頼した場合、節税できるポイントを見落としたり、思ったようなサポートを受けられない可能性もあるので、過去の事例や得意分野を調べてから相談に臨むことも大切です。
不動産相続に関する税理士を選ぶ際にチェックしたいポイント

不動産相続を税理士に依頼する際、どういった基準で選べば良いのでしょうか。
ここでは、税理士を選ぶ際にチェックしたいポイントを次の3点に絞って解説します。
- 不動産相続を得意としているか
- サポート体制は充実しているか
- 費用体系は明瞭か
各ポイントを、詳しく見ていきましょう。
不動産相続を得意としているか
税理士にもそれぞれ得意としている分野があります。
不動産相続に関する実務経験を積んでいる税理士は、最新法令をきちんと把握しているだけでなく、さまざまな情報やノウハウを蓄積しています。
税理士事務所の公式サイトで経歴や過去の事例を確認したうえで、無料相談などで直接話をして見極めることが大切です。
サポート体制は充実しているか
不動産相続は書類の準備や申告手続きなど、多くの作業が発生します。
スムーズに手続きを進めるうえで、問い合わせへのスピーディーな対応や連絡手段の選択肢は大切なポイントです。
次のような項目は相談時にチェックしておきましょう。
- メールやLINEで相談できるか
- 対応受付時間は明記されているか
- 質問に対する回答が的確か
- 必要な手続きや費用、書類について丁寧に説明してくれるか
費用体系は明瞭か
税理士報酬の計算方法は、事務所ごとに異なります。
着手金、成功報酬、固定報酬のいずれかが一般的ですが、事務所によってはこれらを組み合わせた費用体系になっていることも。
費用のことを面と向かって聞くのは気が引けるという方も多いと思います。
トラブルを回避するには依頼前に見積書を作成してもらい、追加費用の有無や費用発生のタイミングを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
費用に関する質問にきちんと答えてくれるかという点も、税理士を選ぶうえで大きなポイントになります。
不動産相続を税理士に依頼した際の費用相場の試算方法

不動産相続を税理士に依頼する際の報酬は、相続財産の総額から算出されるケースが一般的です。
「相続財産の総額×1%」や「基本料金+加算報酬」のように計算されますが、実際には「遺産総額〇〇万円までは〇〇万円」というふうに、段階を分けて報酬を設定しているところが多いようです。
簡易な申告であれば20万円前後で済むこともありますが、土地や建物の評価が複雑な場合は、50万円を超える可能性もあります。
相続人の人数や不動産の数、申告期限までの残り日数なども加算報酬として計算されるため、相談の前に情報を整理しておくことも大切です。
報酬額が相場より高くなるケース
相続不動産の評価に複数回の現地調査が必要な場合、期限直前の対応などが含まれると、報酬が高額になる傾向があります。
また、名義変更や登記関連業務の一部を司法書士と連携して代行するケースでは、別途費用が発生することもあります。
総額だけにこだわらず、依頼した内容と対応範囲から報酬が妥当かを考える視点も必要だといえるでしょう。
不動産相続で税理士に依頼したほうが良いケース

不動産相続を税理士に依頼したほうが良いケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続不動産が複数ある場合
- 土地が共有名義になっているとき
- 相続を巡って争いが生じている場合
- 土地や建物の評価が複雑なとき
- 賃貸物件の引き継ぎがあるとき
- 税務調査や二次相続の心配があるとき
ここからは、それぞれについて詳しくみていきましょう。
相続不動産が複数ある場合
複数の土地や建物を相続する場合、それぞれの評価方法が異なるため、かなりの手間と時間を要します。
立地や形状、道路との接続をそれぞれ確認し、特例や制度を利用できるのか物件ごとに確認していかなければなりません。
誤った評価のまま相続税を申告してしまうと、過少申告や払い過ぎが発生する可能性も。
特に相続で初めて不動産評価に触れるという方は、最初からプロの税理士に依頼することをおすすめします。
土地が共有名義になっているとき
共有名義の土地は、共有名義人の相続人が引き継ぐことになっています。
すぐに処分する予定がない不動産でも、共有名義のまま放置していると相続によって共有名義人が増えるなど、トラブルの原因になることも。
相続をきっかけに共有名義を解消する場合、売却や分筆といった方法が考えられますが、他の共有名義人との交渉が必要になるケースも少なくありません。
税理士であれば、状況に応じた最適な手段を提案してくれるだけでなく、共有名義人とのやり取りについても相談することができます。
さらに、税金対策にも対応してもらえるため、トラブルや損失を防ぐという観点からも、税理士に依頼することをおすすめします。
相続を巡って争いが生じている場合
相続人間で意見が対立している場合、税務処理だけでなく相続手続そのものがストップしてしまう可能性があります。
相続税の申告期限は原則として相続開始から10か月以内と定められており、場合によっては期限に間に合わなくなってしまうことも。
プロの税理士があいだに入ることで、専門家の立場から財産の評価や税額の見積もりを行えます。
専門家の意見が入ることで、感情的な対立をクールダウンさせるという副次的な効果も。
必要に応じて部分的な申告などの提案を行うことで、手続を停滞させず進めていけるという効果も期待できます。
土地や建物の評価が複雑なとき
傾斜地や無道路地、市街化調整区域内の土地、建物付きの物件などは評価が難しく、場合によっては評価誤差が数百万円に及ぶこともあります。
たとえば無道路地は道路に面していないため価値が下がる傾向があり、市街化調整区域内の土地は建築制限があるため、一般の宅地よりも低い評価になります
こうしたケースでは路線価や倍率表にくわえて、補正率や個別事情を加味した評価が必要です。
税理士はこのような特例的な評価方法についての実務経験を積んでいるので、自分たちでは手に負えないような複雑な不動産評価にも対応してもらえます。
賃貸物件の引き継ぎがあるとき
収益物件を相続する場合、相続前後の家賃収入の扱いや管理費・修繕積立金の取り扱いが問題になります。
- 相続手続中に発生した家賃は誰の収入として申告するか
- 敷金や保証金の処理をどうするか
- 相続人が会社員の場合、どのように家賃収入を取り扱うか
他にも確認しなければならない事項が、次々と出てくるでしょう。
相続に関わる税務や申告は、税理士の専門とする分野です。
賃貸物件の相続は今後の税金や申告にも大きく関わってくる問題なので、早めに専門家に相談することが大切です。
税務調査や二次相続の心配があるとき
相続税を申告したあと、内容の不備や疑義があると税務調査が行われることがあります。
不動産評価や申告のミスを最大限防ぎ、税務調査のリスクを下げるには税理士のサポートを受けるほうが良いでしょう。
また、一次相続の内容が二次相続に大きく影響するため、長期的な視点からの節税対策も必要です。
専門知識豊富な税理士に、現在だけでなく遺される家族のことも考えた相続プランを立ててもらうことをおすすめします。
不動産相続で税理士に依頼する際の必要書類
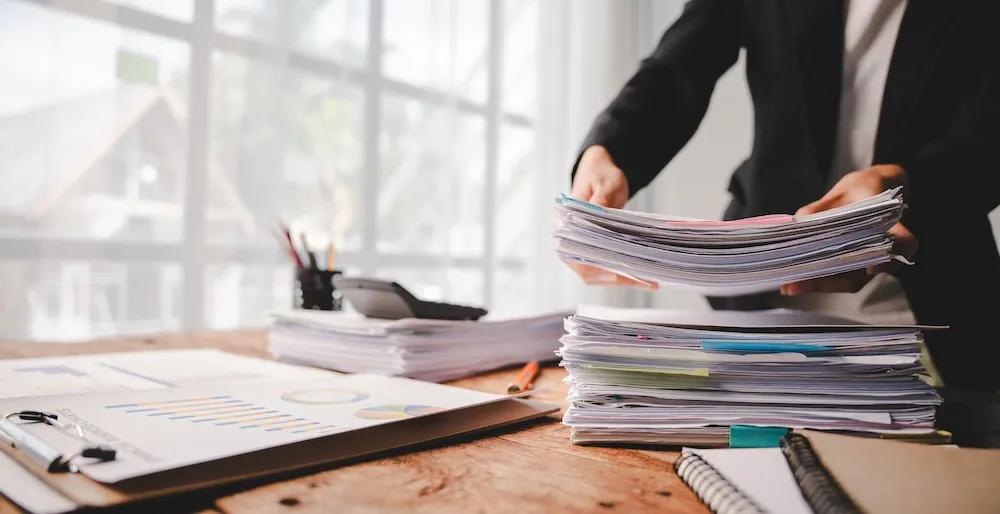
不動産相続を税理士へ相談する際は、相続人や相続財産に関する書類をあらかじめ用意しておくとスムーズです。
一般的に必要とされる書類は、以下の通りです。
- 相談者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 被相続人(なくなった人)の出生から死亡まで記載された戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図
- 遺言書(あれば)のコピー
- 遺産分割協議書のコピー
- 相続する不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 固定資産税課税明細書
- 賃貸借契約書(あれば)
- 建物図面(あれば)
依頼する税理士や不動産の種類、状況によって必要な書類は異なります。
ここに挙げた書類は原則として必要になることが多いものなので、税理士に相談する前に必要書類についても確認しておくことをおすすめします。
相続不動産に関する申告ミスや特例適用は、プロに任せるとスムーズ!

不動産の相続は何度も経験することではないうえ、耳慣れない用語も多いものです。
また、相続財産のなかでも資産価値が高いことが多いため、相続税額に直接影響を与えることも少なくありません。
静鉄不動産は地域に根差した不動産会社として、地元のお客様に寄り添ったサービスを提供してきました。
このたび相続全般のサポートに特化したサービスとして「相続ワンストップサポート」を開始いたしました。
税理士や司法書士をはじめとする相続のプロと連携し、オーダーメイドの相続対策をご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ


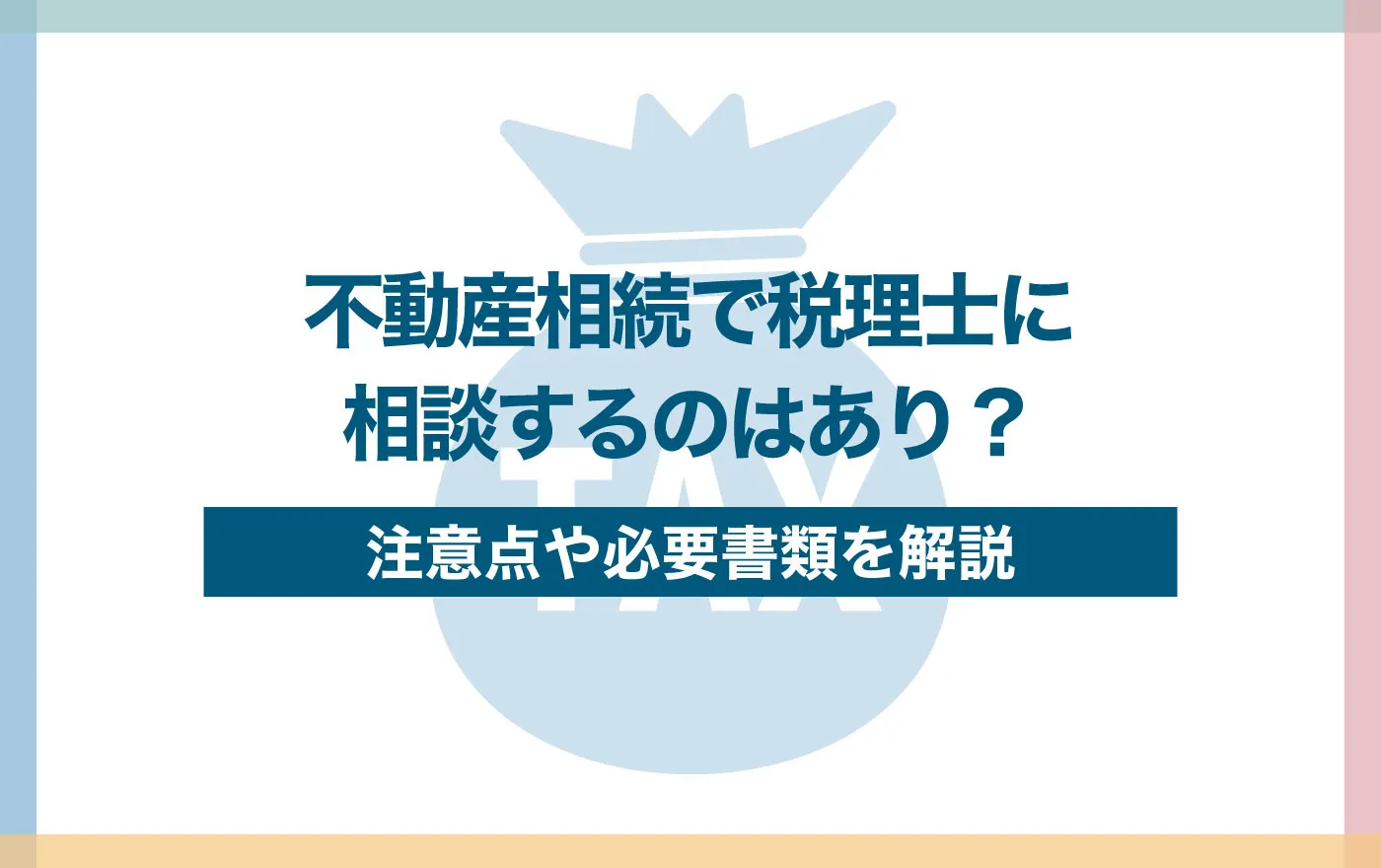


コメント