遺産相続にまつわるトラブルで、相続財産に不動産が含まれているケースがよくみられます。
相続人同士の意見の食い違いや利害の対立が起きてしまい、どのように対処すれば良いかお困りの方も多いのではないでしょうか。
不動産は資産価値が高いだけでなく相続手続きも複雑なため、自分たちだけでトラブルを解決しようとすると、逆に長引いてしまうことも珍しくありません。
この記事では不動産相続におけるトラブル事例や、トラブルを回避するために知っておきたいポイントについて詳しく解説しています。
不動産相続でトラブルが起きやすい理由

不動産は現金や預貯金と異なり、相続財産のなかでも平等に分けづらい部類に入ります。
評価方法には固定資産税評価額、路線価、実勢価格など複数の基準があります。
どれを基準に考えるかは人によって異なるため、相続人全員が納得できる評価にならないことも珍しくありません。
不動産は長年住み慣れた実家や家業の拠点など、感情的な要素が絡みやすい財産でもあります。
「大切な思い出を残しておきたい」という気持ちも「資産として適切に分割したい」という気持ちも、相続人として当然のものです。
しかしこういった意見の相違を抱えたまま話し合いを進めると、相続人同士の関係が悪化してしまうことも。
また、不動産相続では法律や税務の専門知識が必要になります。
誤った知識のままで進めると問題が長期化するだけでなく、登記の未了や権利関係で行き詰ってしまい、売却や活用が進まないケースもあるのです。
遺産分割の難しさと感情的な問題、手続きの複雑さが重なることで、他の相続財産に比べてトラブルが起きやすいといえるでしょう。
不動産相続でよく起きるトラブル

不動産相続においてよく起きるトラブルとして、以下のようなものが挙げられます。
- 評価額の認識違い
- 不動産分割方法に対する方針の違い
- 共有名義や未登記による権利関係の複雑化
- 特定の相続人への不満や対立
- 相続税支払いに対する認識違いや準備不足
- 海外在住の相続人がいることによる連絡・手続き難航化
ここからは、それぞれについて詳しく解説していきます。
評価額の認識違い
固定資産税評価額、路線価、実勢価格のどれを参考にするかで評価額が変わるため、相続人の間で価値に対する認識が一致しないことがあります。
特に市場価格と固定資産税評価額に差がある場合、どちらを基準にするかで意見が割れるケースが多くみられます。
不動産分割方法に対する方針の違い
現物のまま共有にするのか、売却して現金化するのか、あるいは代償分割で調整するのかなど、分割方法の選択は意見が割れやすいポイントです。
例えば「これまで通り自分が住み続けたい」という相続人と、「早く売却して資金化したい」という相続人がいる場合、利害が対立して話し合いが拗れがちです。
共有名義にして分割したとしても、物件の利用や管理を巡って新たなトラブルが発生する事例も多くみられます。
共有名義や未登記による権利関係の複雑化
共有名義になっている土地や、登記がされていない不動産は、権利関係が複雑になっており整理が困難です。
未登記のまま代を重ねている土地は、相続が細分化されて法定相続人が大人数になっています。
こういった場合でも、相続人全員の同意を取って権利関係を整理しないと手続きを進めることができません。
相続人の確定や連絡だけでかなりの時間を要してしまい、肝心の遺産分割をなかなか始められないというトラブルも多くみられます。
特定の相続人への不満や対立
相続でよくみられるのが介護や家業への貢献、被相続人との関係性によって「自分は他の相続人より多くもらうべきだ」という主張です。
実際のところ、裁判等で生前の貢献が相続に反映された事例はさほど多くありませんが、
金額の大小ではなく感情的な問題は客観論で解決しづらいものです。
話し合いが感情論に流れてしまうと、当事者のみで円満に解決するのは難しいでしょう。
相続税支払いに対する認識違いや準備不足
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に現金で一括納付する必要があります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
そのため、納税資金の準備が間に合わず、相続税の支払いが問題になるケースもあります。
なお、相続税の申告・納税義務は、相続財産が基礎控除額を超える場合に生じるもの。
基礎控除額は法定相続人の数等に応じて計算されます。
代償分割で調整する場合も、誰が納税資金を負担するか、どの評価額を基準にするかなどで意見が食い違い、協議がこじれるケースがあります。
海外在住の相続人がいることによる連絡・手続き難航化
相続人に海外在住者が含まれると、通常よりも相続手続きに時間がかかります。
相続登記等に必要な印鑑証明書は日本国内でしか取得できないため、現地大使館で署名証明書を作成しなければなりません。
委任状や同意書に公証を受けて郵送する手間や現地との時差で、書類を揃えるのに数か月かかるケースも珍しくありません。
売却や名義変更の手続きは相続人全員の同意が必要なため、一人でも承認が遅れると手続き全体が止まってしまいます。
こうした状況が長引くと、他の相続人が不満を募らせ関係が悪化したり、固定資産税や維持費の負担だけが続いて経済的な損失が出る可能性も。
海外に相続人がいる場合は、早い段階で必要な書類や手続きを確認し、情報を共有しておくことをおすすめします。
場合によっては海外の手続きに強い専門家に相談することも視野に入れましょう。
トラブルが起こりやすい相続不動産の特徴

トラブルが起こりやすい相続不動産の特徴には、以下のようなものがあります。
- 共有名義や利用目的の異なる不動産
- 再建築不可、借地権付きなど売却が難しい不動産
- 管理されていない地方の空き家や放置物件
- 相続人が多すぎたり、人間関係がこじれている不動産
- 資産価値が高い不動産
以下からは、それぞれについて詳しく解説していきます。
共有名義や利用目的の異なる不動産
共有名義にした土地や建物は、土地活用や売却に関して意見が分かれやすい資産です。
共有者全員の同意がなければ売却や活用ができないため、一人でも反対すると手続きが進みません。
また、誰かが自宅として使いたい場合と、売却したい相続人がいる場合も利害が一致しにくく、協議が長期化することがあります。
再建築不可、借地権付きなど売却が難しい不動産
建築基準法上の制約で再建築ができない土地や、借地権が付いている不動産は、相続後の活用や売却が難しい部類に入ります。
需要が限られるので評価額が低くなり「本当に売る意味があるのか」「もっと高値で売れるのではないか」など意見が割れやすくなる傾向も。
特に借地権付きの土地では、地権者との交渉がトラブルに発展するおそれもあります。
管理されていない地方の空き家や放置物件
地方にある空き家や長期間管理されていない放置物件は、相続後も活用の見込みが立たず、トラブルが頻発しています。
市町村長が「特定空家等」に対して助言・指導・勧告・命令を行い、命令に従わない場合には行政代執行(強制撤去など)を実施できると定められています。
第14条 空家等の管理に関する民法の特例
2 市町村長は、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
放置された空き家は固定資産税がかかるだけでなく、倒壊の危険や犯罪の温床になるなど、近隣にも影響が及ぶ問題へ発展するおそれがあります。
相続人が多すぎたり、人間関係がこじれている不動産
法定相続人の数が多いと意見のすり合わせが難しく、それだけで遺産分割協議の難易度が上がります。
特にもともとあまり仲が良くない親族同士の場合、感情面での対立が原因で話し合いが進まず大きなトラブルになることも。
こうしたケースでは専門家や法的手段を用いるなど、第三者を介したほうがスムーズに解決する可能性もあります。
資産価値が高い不動産
市街地にある土地や収益が期待できる賃貸物件など資産価値が高い不動産は、相続人のあいだで取り合いになってしまう傾向があります。
また、評価額が大きいほど分割方法に対する意見も割れやすく、代償分割や売却益の配分を巡ってトラブルに発展するケースが目立ちます。
不動産相続におけるトラブルと解決例

不動産相続におけるトラブルには、以下のようなものがあります。
- 共有名義で意見が分かれ売却が進められない
- 評価額の認識が異なり、代償金額で争いが起きた
- 遺産分割協議書が無効とされ、遺産分割がやり直しになった
- 土地建物を平等に分割できず、相続人から不満が出た
- 不動産を占拠している相続人がいる
ここからは、トラブル事例と解決策について詳しくみていきましょう。
共有名義で意見が分かれ売却が進められない
相続した不動産を共有名義にした結果、売却や活用の方針が合わず手続きが止まってしまうことがあります。
共有名義の不動産を処分するには全員の同意が必要なので、一人でも反対者がいると売却できなくなってしまいます。
解決策として、遺産分割協議で単独所有に変更するか、家庭裁判所の調停を利用して全員の合意を取り付けるなどの対策が必要でしょう。
評価額の認識が異なり、代償金額で争いが起きた
不動産の評価基準をめぐって相続人間で金額が一致せず、トラブルへ発展する事例も少なくありません。
こういった場合、複数の不動産鑑定や路線価を用いて客観的な評価額を出し、互いに折り合いをつける解決法がとられます。
それぞれの主観ではなく客観的な数字を共有したうえで、評価方法を統一することが大切です。
遺産分割協議書が無効とされ、遺産分割がやり直しになった
協議書の形式不備や相続人の署名漏れ、協議に参加していない相続人がいると、遺産分割協議書が無効になる可能性があります。
この場合、はじめから遺産分割協議をやり直すことになるため、二度手間になってしまいます。
正確に手続を行うには、司法書士や弁護士に書類の収集や作成代行を依頼するのもひとつの方法です。
土地建物を平等に分割できず、相続人から不満が出た
不動産は物理的に分けることができないので、相続財産のなかでも不公平感が生じやすい部類といえます。
平等に分配することを目指すのであれば、売却して現金化するか、代償分割で調整するのが一般的です。
相続人全員が納得できるよう、司法書士など専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
不動産を占拠している相続人がいる
相続財産である家に相続人が住み続け、他の相続人と協議が進まない例もあります。
相続人による占拠は明け渡しの請求が難しいため、話し合いで解決できなければいつまでも占拠されたままになってしまいます。
早めに専門家に相談して、法律に則った対応を進めることをおすすめします。
不動産相続でのトラブルを未然に防ぐために知っておきたいポイント

不動産相続のトラブルを未然に防ぐためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- 遺言書を作成する
- 相続人同士のコミュニケーションを密にする
- 生前贈与や家族信託の活用
ここからは、それぞれについて詳しく解説していきます。
遺言書を作成する
遺言書は被相続人(亡くなった方)の遺志を明記したもので、相続において最も効力が強い書類です。
第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる
引用元:民法 | 民法第902条
なお、自筆遺言書・秘密証書遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認・開封が必要です。
違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
遺言書に相続財産の分け方や受け取る人を明確に記載しておくことで、相続人同士の争いを大幅に減らす効果が期待できます。
特に不動産は価値や利用方法を巡って意見が割れやすいので、事前に方向性を示しておくことは非常に重要だといえるでしょう。
相続人同士のコミュニケーションを密にする
相続人同士でコミュニケーションを取りお互いの考え方を知っておくのは、トラブルを防ぐうえで非常に大切なことです。
亡くなる前から相続のことを話すのは不謹慎ですが、日頃の会話などからいずれ相続する不動産に対してどういった考えを持っているのか知ることもできるでしょう。
特に不動産は複雑な感情が絡むものなので、相続人同士の意見やスタンスを早めに把握しておくことをおすすめします。
生前贈与や家族信託の活用
不動産のように平等に分配することが難しい財産は、生前贈与や家族信託で管理や承継方法を早い段階で決めておくと安心です。
生前贈与は税負担を分散できるメリットが、家族信託には認知症など将来的なリスクに対応できるというメリットがあります。
被相続人から財産分配の意向を直接聞けるので、相続人にわだかまりが残りにくいというのも共通のメリットといえるでしょう。
不動産相続トラブルが起きたときの相談先

不動産相続トラブルが起きたら、どのようなところに相談すれば良いのでしょうか?
- 司法書士や弁護士など法律のプロに相談する
- 場合によっては調停や裁判も検討する
ここからは、それぞれについて詳しく解説していきます。
司法書士や弁護士など法律のプロに相談する
不動産相続では登記や権利関係の整理、協議書の作成など慣れない手続きが多数必要になります。
司法書士は登記や書類作成の専門家として、相続初期から相続登記まで幅広く相談することができます。
法的トラブルに発展しそうなときは、弁護士に相談すると良いでしょう。
問題が複雑化する前に専門家へ相談することで、解決までの時間や負担を大幅に減らすことができます。
場合によっては調停や裁判も検討する
話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用して第三者の仲介を受ける方法があります。
調停で解決しない場合は、裁判で法的な判断を仰ぐことになります。
調停や裁判というと怯んでしまう方も多いと思いますが、いったん拗れてしまった話し合いを当事者だけで円満にまとめるのは困難です。
専門家のサポートを受けつつ、法的な手段で解決することも検討してみましょう。
不動産相続にまつわるトラブルはプロに相談しましょう

故人の遺した不動産を適正に相続したいというのは、相続人誰しもに共通する願いです。
それだけに意見や利害の不一致から、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターが提供する「相続ワンストップサポート」は、不動産相続に直面したお客様のお困りごとを解決するサービスとして、多くのお客様から高いご支持をいただいています。
不動産相続にお困りの方は、どうぞお気軽に当社までご相談ください。
電話でのお問い合わせ


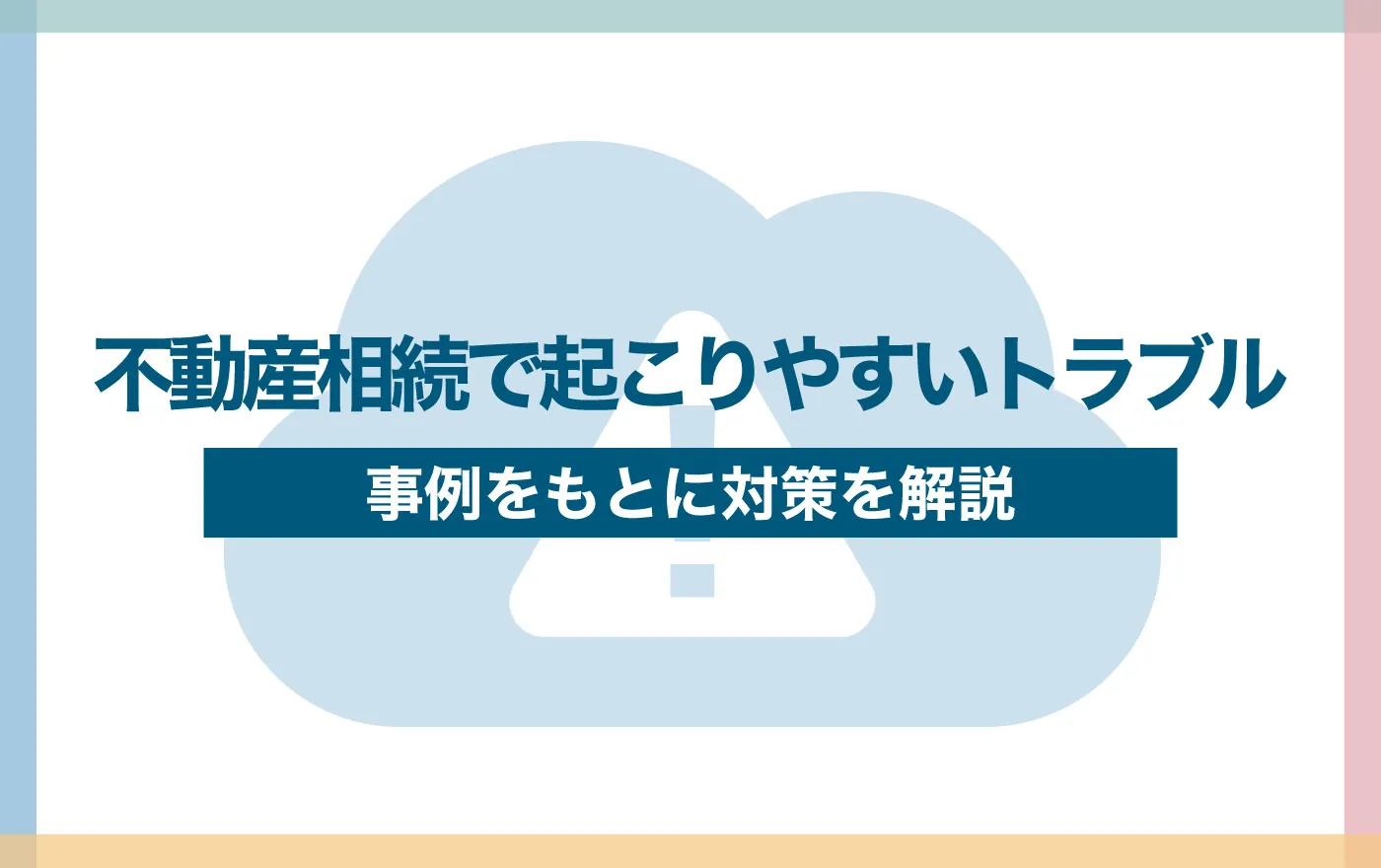


コメント