生前贈与とは、相続が発生する前に不動産などの財産を子どもや孫へ贈与し、その名義を移しておくことを指します。
親などが元気なうちに、希望通りに財産を引き継ぐ手段の一つとして利用される方法です。
亡くなった後に行う相続手続きに比べると手間が少なく、トラブル防止や節税対策として検討されることが多い方法です。
生前贈与によって贈与時点で名義変更を行うため、その時点から不動産の所有権は受け取った側(受贈者)に移転します。
この記事では、生前贈与による不動産の名義変更について、その目的やメリット・デメリット、具体的な手続きの流れや注意点、必要書類まで詳しく解説します。
生前贈与で不動産の名義変更を行う目的

生前贈与を活用して不動産の名義をあらかじめ変更しておく主な目的は、主に次の3点です。
| 目的 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 相続発生後の名義変更の手間を軽減するため | ・生前に名義を移しておけば、相続発生後に不動産の相続登記などを行う必要がなくなる ・相続時の手続きや書類準備を事前に済ませられる |
相続開始後の事務負担を軽減し、残された家族の手続きをスムーズにする |
| 遺産分割を巡る争いを防ぐため | ・不動産は現金のように分割できず、相続時に「誰が引き継ぐか」で揉めることが多い ・生前に名義変更しておけば、遺産分割協議でもめるリスクや共有名義による売却困難を回避できる |
親族間のトラブルを未然に防ぎ、円満な財産承継を実現できる |
| 相続税の負担を軽くするため | ・将来的に価値が上がる不動産を早めに贈与すれば、相続時の課税対象から除外でき、節税効果が見込める ・家賃収入などの利益も早めに受贈者側に移すことで、贈与者の相続財産を減らす効果がある |
相続税の課税額を抑え、財産をより多く残すことができる |
特に、家族内で「誰がどの不動産を引き継ぐか」を生前に決めておくことは、相続時のトラブルを事前に回避できるため利点です。
親族間の争いを避け、スムーズな財産承継を行うために、生前贈与による名義変更が検討されるのです。
生前贈与と相続の使い分け方

生前贈与は節税やトラブル回避の観点でおすすめな手段です。
しかし、すべてのケースに最適とは限りません。
贈与税の負担が重くなりすぎたり、他の相続人との公平性、バランスを欠いてしまったりする場合もあるためです。
まず、生前贈与の際にネックになるのが贈与税です。
贈与税は基礎控除額である年間110万円を超える贈与に対して課税され、課税額は金額に応じて高率になります(たとえば基礎控除後の課税価格が200万円以下なら税率10%、1,000万円以下なら40%、3,000万円超では55%もの税率)。
ただし、実務で多い親から子・孫への贈与は特例税率が適用され、たとえば1,000万円以下の部分は30%の税率区分が含まれます。
評価額の高い不動産を生前贈与すると多額の贈与税がかかるケースも多く、贈与によってかえって税負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
また、生前に特定の相続人へ不動産を贈与すると、他の相続人との公平性にも配慮しなくてはなりません。
生前贈与で受け取った利益は「特別受益」とみなされ、遺産分割の際に他の遺産と合算して計算されるため、贈与を受けた人の相続分が減ってしまう可能性があります。
たとえば長男が生前に土地を贈与されていた場合、後日の遺産分割協議ではその価値を考慮して他の兄弟の取り分を増やす調整(持ち戻し計算)が行われることがあります。
このように、他の相続人との公平を損なう恐れもあるため、生前贈与を行う際は家族全体で十分に話し合うことが大切です。
さらに、税制面でも相続の方が有利になるケースがあります。
たとえば、被相続人と同居の自宅土地など一定の不動産については相続時に評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できる場合がありますが、この特例は生前贈与には適用されません。
要件を満たせば相続による取得の方が税額を大幅に減らせる場合もあるため、単純に「贈与すれば得」「相続の方が損」とは言い切れません。
生前贈与と相続のどちらが適切かは状況によって異なります。
不動産の評価額や他の財産、家族構成、将来の資金計画などを踏まえて、綿密なシミュレーションが必要です。
不安な場合は税理士など専門家に相談し、贈与と相続のメリット・デメリットを比較検討すると良いです。
【対策あり】年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる

生前贈与を検討する際に最も注意すべきポイントの一つが贈与税です。
冒頭で触れたとおり、贈与税には年間110万円の非課税枠(基礎控除)があり、110万円を超える贈与には贈与を受けた人(受贈者)に対して課税が発生します。
不動産のように評価額が高額になりやすい財産では、この110万円を超える部分について高い税率で贈与税が課されるため、事前に税額を試算しておくことが重要です。
贈与税の負担を抑える対策として代表的なのが、「相続時精算課税制度」の活用です。
相続時精算課税制度は一定の要件の下で選択できる制度で、生前に贈与税を納める代わりに相続時にまとめて精算する仕組みになっています。
相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となり、超過分に一律20%が課税されます。
また、贈与財産は贈与時評価で相続財産に加算して相続税を計算します。
相続時精算課税制度を利用すれば、大きな不動産であっても最大2,500万円までは贈与税がかからずに移転できるため、一時的な贈与税負担を大幅に軽減が可能です。
ただし、非課税だからといって完全に税金がゼロになるわけではなく、贈与した財産は相続時に清算される(課税を先送りする)制度である点に注意が必要です。
また一度選択するとその贈与者との間では元の暦年課税(毎年110万円控除の制度)に戻れないことや、小規模宅地特例が使えなくなるなどのデメリットもあります。
2024年贈与分からは、相続時精算課税を選択していても「年110万円までの贈与は申告不要・非課税」の取り扱いが導入されています。
また、生前贈与の相続税加算期間は「死亡前7年」に拡大されています。
相続時精算課税の適用要件や手続きは複雑なため、利用を検討する際は税理士に相談し、自分たちのケースで本当に有利か慎重に判断しましょう。
生前贈与による不動産の名義変更の流れ

生前贈与によって不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う場合、その手続きは相続登記とは異なり「贈与契約」に基づいて進める必要があります。
一般的な流れは次のとおりです。
| 手続き段階 | 主な内容 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 贈与契約書の作成 | ・贈与者(渡す人)と受贈者(受け取る人)の間で、不動産贈与に関する契約書を作成する ・契約書には不動産の所在地・評価額・贈与時期・条件を明記し、双方が署名押印する |
・口頭でも贈与は成立するが、トラブル防止のため必ず書面で作成すること ・署名は手書き、押印は実印が望ましい ・契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要がある ・この契約書は「登記原因証明情報」としても使用される |
| 登記申請書の作成・提出 | ・不動産の所有権移転登記を行うため、法務局に提出する登記申請書を作成 ・所在地・地番・登記原因(贈与)・日付・贈与者と受贈者の情報を記載する |
・必要書類を揃え、不動産所在地を管轄する法務局へ提出する ・本人申請も可能だが、書類不備を避けるため司法書士に依頼するのが安全 |
| 登録免許税の納付 | ・登記の際に必要な税金 ・贈与による所有権移転登記では、不動産の固定資産税評価額の2%が課税される |
・例:評価額3,000万円の場合、登録免許税は60万円 ・登記申請書に収入印紙を貼付して納付する ・贈与税や不動産取得税とは別に必要な税金である ・事前に固定資産評価証明書で税額を確認しておくこと |
| 名義変更の完了・各種変更手続き | ・登記が完了すると、登記名義人が贈与者から受贈者に変更される ・登記識別情報通知(新しい権利証)が発行される |
・名義変更後、固定資産税・都市計画税の納税義務は受贈者へ移転 ・固定資産税の送付先変更や水道・電気などライフラインの名義変更も行うこと ・登記識別情報通知は権利証として大切に保管する |
以上が生前贈与による不動産名義変更の基本的な流れです。
なお、作成した贈与契約書はできれば公正証書にしておくことが望ましいです。
公証役場で契約書を公正証書にしておけば、契約内容の信頼性が高まり原本も公証役場で保管されるため、万一契約書を紛失した場合でも安心できます。
贈与契約書を公正証書にすると証拠能力が高まります。
後日の「言った言わない」の争いや税務署からの確認にも確実な対応が可能です。
名義変更後の固定資産税の支払い義務に注意

生前贈与による名義変更が完了すると、受贈者は新たな不動産の所有者となります。
そのため、贈与を受けた翌年度からは当該不動産にかかる固定資産税・都市計画税の納税義務が受贈者に移ります。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される税金で、一般的に固定資産税評価額の1.4%(標準税率)、都市計画税は0.3%が課税される仕組みです。
名義変更後初めての年度には、市町村から受贈者宛てに納税通知書が届きます。
前所有者と連絡を取り合いながら漏れなく手続きを行いましょう。
また、将来的にその不動産を売却する場合にも注意が必要です。
生前贈与で取得した不動産を売却する際の譲渡所得税の計算では、基本的に贈与者が当初取得した時の購入費用(取得費)を引き継ぐ形です。
たとえば、親が1,000万円で購入した土地を子に贈与し、子がその土地を後に3,000万円で売却した場合、取得費は親の購入額1,000万円を引き継ぐため、売却益は約2,000万円とみなされます。
その結果、譲渡所得税が高額になる可能性があります(相続で取得した場合には、一定条件下で相続税額を取得費に加算できる特例がありますが、生前贈与で取得した場合はこの特例が使えません)。
このように、生前贈与を受けた不動産の売却時には思わぬ税負担が発生し得るため、早い段階で税理士に相談しシミュレーションしておくと安心です。
贈与税・相続税・譲渡所得税と複数の税金が関わるケースに該当するので、税務の専門家に計算を依頼し、最適なタイミングや方法を具体的に決めましょう。
なお、名義変更後に固定資産税を新所有者(受贈者)が支払うことになる点について、ご家族内で事前に共有しておくことも大切です。
贈与により不動産を譲り受けても、維持管理費や税金の負担が発生することを理解した上で、贈与後の資金計画を立てましょう。
生前贈与による不動産の名義変更の登記に必要な書類
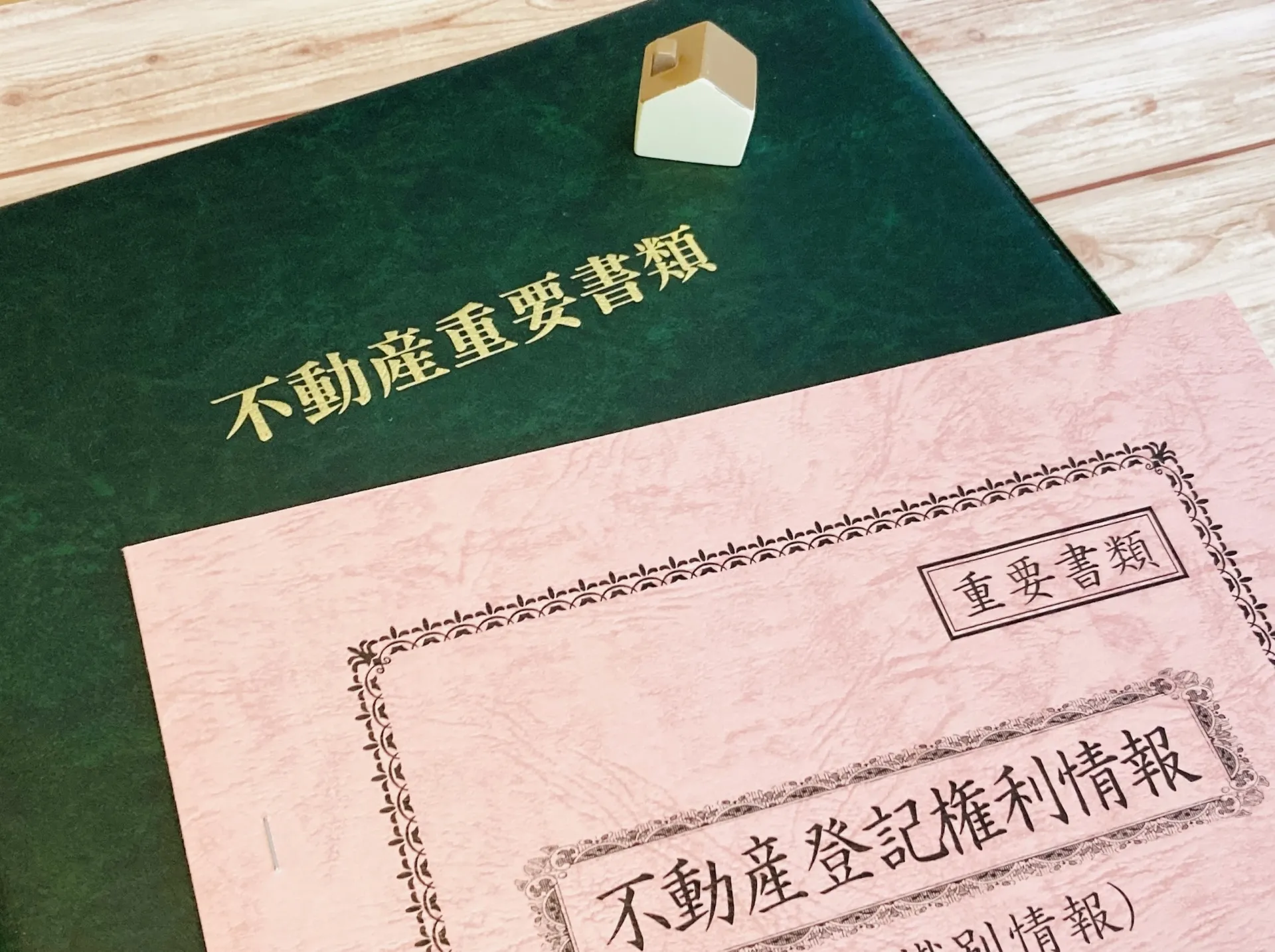
不動産の生前贈与に伴い所有権移転登記を行う際には、以下表のような書類を用意する必要があります。
登記申請書と合わせて各書類を贈与者の住所地(または不動産所在地)を管轄する法務局に提出しましょう。
| 書類名 | 内容・概要 |
|---|---|
| 登記申請書 | ・登記手続きを行うための申請書 ・贈与による所有権移転登記用の書式に必要事項を記入し、贈与者・受贈者が署名押印する(司法書士に依頼する場合は司法書士が作成します) |
| 贈与契約書(登記原因証明情報) | ・贈与の事実を証明する書面 ・通常は当事者間で締結した贈与契約書がこの証明書 ・原本を提出し、登記完了後は原則返却されないのでコピーを保管しておく |
| 登記済権利証または登記識別情報 | ・贈与者側で保管している不動産の権利証(古い登記済証)あるいは登記識別情報通知書 ・現在の所有者だけが保有できる書類であり、登記申請の際に提出(または情報を提供)することで、本人確認の証拠として用いられる |
| 固定資産評価証明書 | ・不動産の市町村役場で発行してもらえる、その年度の固定資産税評価額を証明する書類 ・登録免許税額の算定に使用する ・年度途中で評価替えが行われている場合は、登記申請時の最新年度の評価証明書が必要 |
| 贈与者の印鑑証明書 | ・贈与者(旧所有者)の実印の印鑑証明書 ・発行日から3ヶ月以内の原本を用意する ・贈与という重要な財産処分行為であるため、贈与者本人の実印押印と印鑑証明の提出が求められる |
| 受贈者の住民票(住所証明書) | ・受贈者(新所有者)の住所を証明する書類として住民票の写しを提出する ・登記簿に登録する新所有者の住所氏名を確認するために必要 ・住民票は発行日からの期限は特にありませんが、住所や氏名に変更がない最新のものを用意する(戸籍附票や受贈者の印鑑証明書で代用も可) |
| 贈与者・受贈者それぞれの本人確認書類 | ・登記申請を本人で行う場合は、窓口で運転免許証など写真付きの本人確認書類の提示が求めらる ・司法書士に依頼する場合も、委任状に添付する形で両者の本人確認資料のコピー(運転免許証等)が必要 |
以上の書類をすべて揃えて、初めて登記申請が受理されます。
不動産ごとに必要書類が異なる場合や追加書類(例:農地を贈与する場合の許可証など)が必要となるケースもありますので、具体的には法務局や司法書士に確認すると確実です。
書類の不備や不足があると申請がスムーズに進みませんので、事前にチェックリストを作成して漏れのないよう準備しましょう。
不動産の生前贈与による名義変更は専門家と相談した上で安心して進めよう!

ここまで、生前贈与による不動産の名義変更について、目的やメリット・デメリット、手続きの流れ、注意点、必要書類まで解説しました。
不動産の生前贈与による名義変更は、相続対策として有効である一方、税金計算や登記手続きに専門的な知識を要する複雑な面があります。
贈与契約書の作成から登記申請、贈与税・相続税の申告に至るまで正確に行う必要があるため、早めに専門家へ相談することが不可欠です。
実際に贈与や相続の手続きを進める段階になると、「誰に相談すればいいのか」「どこまで自分で対応できるのか」と迷う方が多いのも事実です。
もし静岡県内で相続や不動産に関するお悩みを抱えている方は、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへぜひご相談ください。
静岡鉄道グループは2019年に創立100周年を迎えており、100年にわたって培った静岡地域での信頼と実績を背景に、相続に関するあらゆる知識とネットワークを駆使してサポートいたします。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、不動産のプロである静鉄不動産が窓口となり、提携する司法書士・税理士・弁護士など各分野の専門士業が連携してワンストップで対応が可能です。
生前贈与の活用による相続税対策の立案から、登記・税務申告、将来的な遺産整理まで、一貫してお任せいただけます。
静岡に根ざした企業ならではのきめ細やかな対応と、グループ総合力による安心・安全・高品質なサービスで、皆様の大切な財産承継をお手伝いいたします。
生前贈与はタイミングを逃すと効果が薄れる場合もあるため、早めの対策開始が肝心です。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
電話でのお問い合わせ





コメント