相続財産のなかで扱いが難しいものとして、不動産が挙げられます。
「親から土地を相続したが使い道がなく困っている」「管理にも手間がかかるし売却したいが、どこから手をつければ良いか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
土地の売却には複雑な手続きも多いため、プロに相談するのもひとつの方法です。
この記事では相続した土地を売却するときの流れや、注意したいポイントについて詳しく解説します。
相続した土地は相続登記が完了していないと売却できない

相続した土地を売却するには、相続登記が完了していないと手続きを進めることができません。
さらに「複数の相続人がいる場合は全員の同意が必要」という要件も満たす必要があります。
ここからは、なぜ相続人全員の同意が必要なのか詳しく解説します。
複数の相続人がいる場合は全員の同意が必要
相続した土地を売却するのにあたり、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要です。
土地は共有財産として扱われるため、一部の相続人が単独で売却を進めることはできません。
売却するには土地を誰が相続するか、もしくは売却して現金で分けるかを相続人全員で協議して決定する旨が法律で定められています。
第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
引用元:民法 | 251条
売却を選択する場合は、相続登記で相続人名義に変更したうえで、全員の合意を確認する手順を踏まなければなりません。
意見がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判に発展することもあります。
相続人の人間関係や財産の状況によっては、専門家を介して協議を進めたほうがスムーズに進むケースも多くみられます。
相続した土地を売却するまでの4ステップ

相続した土地を売却するには、以下の4ステップを経る必要があります。
- ステップ1:相続登記を行う
- ステップ2:土地の状況を調査する
- ステップ3:不動産会社に査定を依頼する
- ステップ4:媒介契約を結んで売りに出す
ここからは、それぞれの項目について詳しくみていきましょう。
ステップ1:相続登記を行う
被相続人(亡くなった人)の名義のまま、土地の売買契約を締結することはできません。
そのため、まずは相続登記を完了させ、相続人名義に変更することから始めましょう。
相続人が複数いる場合は、誰かが土地を取得したうえで売却手続きに移ることになります。
相続登記には以下のような書類が必要です。
| 必要書類 | 取得場所 | 期間 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで記載されたもの) | 本籍地の市町村の役所 | 窓口:即日交付 郵送:1週間~10日程度 |
| 被相続人の住民票の除票 | 居住地の市町村の役所 | 窓口:即日交付 郵送:1週間~10日程度 (死亡届受理後1週間程度) |
| 不動産を取得する人の住民票 | 居住地の市町村の役所(※) | 窓口:即日交付 郵送:1週間~10日程度 |
| 相続人全員の印鑑証明 (遺言書がある場合は不要) |
居住地の市町村の役所(※) | 印鑑登録証を持っていれば即日発行 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地もしくは居住地の市町村の役所(※) | 窓口:即日交付 郵送:1週間~10日程度 |
※マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアでも取得可能
2024年4月から、相続登記が法律により相続登記が義務化されました。
相続開始から3年以内に手続きをしないと、過料が科される可能性があります。
第七十六条の二(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
引用元:民法 | 76条の2
なお、自筆遺言書・秘密証書遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認・開封が必要です。
違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
売却の有無にかかわらず、相続登記は早めに取りかかりましょう。
ステップ2:土地の状況を調査する
土地の売却にあたり、現状の調査を行います。
- 境界が不明確な部分はないか
- 登記されていない建物や把握していない残置物はないか
- 県有地などが含まれていないか
以下のような点を調査していきます。
土地の範囲や権利関係を確認するためには、以下のような書類を取り寄せると良いでしょう。
| 必要書類 | 取得場所 | 期間 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 不動産所在地の法務局(窓口・郵送・オンライン) | 窓口受け取りで3~4時間 郵送受け取りで1~3日 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役所 | 即日発行 |
隣地との境界がはっきりしていない場合など、専門的な調査が必要な場合は土地家屋調査士に依頼するのもひとつの方法です。
ステップ3:不動産会社に査定を依頼する
書類の準備や調査と並行して、不動産会社に査定を依頼します。
不動産会社によって得意なエリアや、取り扱い実績はさまざまです。
相続不動産の売却に強い会社を選ぶことが大切ですが、場合によっては複数の会社に相談することも検討しましょう。
この時点で相続登記が済んでいなくても、査定や相談を進めることは可能です。
ただし、売買契約時に相続登記が完了していないと契約を締結することができないので注意が必要です。
ステップ4:媒介契約を結んで売りに出す
依頼する不動産会社を絞ったら、媒介契約を結んで正式に売却活動を開始します。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ活動範囲や報告義務が異なります。
| 契約の種類 | 契約できる会社の数 | 直接取引 | 報告義務 |
|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1度以上 |
| 専任媒介 | 1社のみ | 可 | 2週間に1度以上 |
| 一般媒介 | 複数 | 可 | 報告義務なし |
契約を結ぶ際は、仲介手数料や広告方針、販売戦略について具体的に確認しておくことが重要です。
地域の事情に精通しており、売却経験が豊富な会社に依頼するのが望ましいでしょう。
相続した土地を売却したときにかかる費用について知っておきたいこと

相続した土地を売却する際にかかる費用について知っておきたいのは、以下の4点です。
- 譲渡所得税の計算方法
- 登録免許税や印紙税などの諸費用
- 所有期間による税率の違い
- 3,000万円特別控除の適用要件
ここからはそれぞれについて詳しくみていきましょう。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税とは、土地を売却した際に発生する税金です。
譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。
計算式は以下の通りです。
譲渡所得=譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費として含まれるのは、以下のような費用です。
- 土地の購入費用
- 登録免許税、不動産取得税、印紙税
- 立ち退き料
- 造成費用
- 測量費用
- 所有権確保等に要した訴訟費用
- 建物の取り壊し費用
- 土地購入のための借入資金の利子(使用開始までの部分のみ)
- 別の不動産の購入契約を解除して不動産を取得した場合の違約金
(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の取得に際して支払った土地の測量費
(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6)建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
(7)土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
相続した土地では取得費が不明な場合が多く、その場合は売却額の5%を概算取得費として扱う制度が適用されます。
譲渡所得税は所得税と住民税を合わせて課税され、所有期間によって税率が変わります。
登録免許税や印紙税などの諸費用
土地を売却する際は譲渡所得税にも、登録免許税や印紙税などの諸費用が発生します。
相続登記を行う際は、固定資産税評価額に0.4%を掛けた登録免許税が必要です。
売買契約書に貼る印紙の税額は契約金額に応じて、以下のように定められています。(※軽減措置適用済)
- 1,000万円以下:5,000円
- 5,000万円以下:10,000円
- 1億円以下:30,000円
- 5億円以下:60,000円
司法書士報酬、測量費用、場合によっては残置物の撤去費なども諸費用に含まれます。
諸費用は事前に見積もりを取り、売却益から差し引いて考えるようにしましょう。
所有期間による税率の違い
譲渡所得税の税率は、不動産を保有していた年数によって異なります。
所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得として扱われ、所得税率は30%です。
これに対し、5年を超えて保有していた場合は長期譲渡所得となり、所得税率は15%と短期より低く設定されています。
不動産を売却して得た利益には、事業所得や給与所得とは別に計算される「分離課税」が適用されます。
売却によって利益が発生した場合、その金額は譲渡所得として扱われ、所得税と住民税の対象になります。
3,000万円特別控除の適用要件
相続した土地に建物があり、一定の条件を満たす場合には3,000万円特別控除が適用されることがあります。
特に「被相続人が一人暮らしで住んでいた住宅」を売却する場合に認められるケースが多いです。
ただし、売却前に居住していた人がいない、または相続開始後に誰かが住んでしまった場合は適用されないなどの条件が、法律により細かく決められています。
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
制度を利用できるかどうか、事前に専門家に相談することをおすすめします。
相続から3年以内に使える節税特例
相続税が課された不動産を3年10か月以内に土地を売却すると、取得費加算の特例を使えることがあります。
相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得を圧縮し税額を抑える効果が期待できます。
また、条件を満たす市街化区域内の低未利用地では、100万円の特別控除を受けられる制度もあります。
これらの特例は期限や要件が細かく決められているため、売却のスケジュールを立てる段階からしっかり確認しておくようにしましょう。
どうしても相続した土地の売却が難しい場合はどうすれば良い?

相続した土地がどうしても売りづらい場合の対策として、以下の2つが挙げられます。
- 賃貸・駐車場・太陽光発電などで収益化を目指す
- 固定資産税対策を必ずする
ここからは、それぞれについて詳しく解説していきます。
賃貸・駐車場・太陽光発電などで収益化を目指す
相続した土地が売却しづらい場合は、賃貸や駐車場経営、太陽光発電用地として収益化を目指すという選択肢があります。
土地の形状や立地で住宅地として使いづらい土地も、駐車場の需要を見出せるケースも考えられます。
太陽光発電用地は長期的に安定した収益が期待できますが、地域の規制や設備投資、周辺住民への配慮などを総合的に考えることが必要です。
場合によっては、土地運用や法律の専門家のアドバイスを受けることも視野に入れて判断することをおすすめします。
固定資産税対策を必ずする
売却まで時間がかかる場合や、当面売れそうにない土地を所有し続ける場合は、固定資産税の負担を軽減する工夫が必要です。
特に更地は住宅用地に比べて課税額が高くなるため、放置していると固定資産税だけがかさむ結果に。
場合によっては土地を一時的に貸し出すことで住宅用地の特例が適用され、税負担を下げられるケースもあります。
固定資産税は毎年発生するため、売却が長期戦になりそうだと感じた時は節税対策も並行して行うようにしましょう。
相続した土地の売却で起きやすいトラブル

相続した土地の売却で起きやすいトラブルとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続人の意見や利害が対立している
- 売却価格に納得できない相続人がいる
- 土地の境界や権利関係が複雑で調査が難航する
以下からは、それぞれについて詳しくみていきましょう。
相続人の意見や利害が対立している
相続した土地をどのように扱うか、相続人のあいだで意見が対立するケースは非常に多くみられます。
一部の相続人は現金化を希望しているが、他の相続人が土地を維持したいと考えているなど意見が割れている場合、当事者だけで協議を完結させるのは難しいでしょう。
こうした対立は感情的な諍いに発展しやすいため、早い段階で専門家を交えた遺産分割協議を行うのがベストです。
専門家からのアドバイスを受けられるという点にくわえて、中立的な第三者がいることでお互い冷静になれるというのもメリットのひとつです。
売却価格に納得できない相続人がいる
査定結果や売却価格に不満を持つ相続人がいると、売買契約の締結が遅れたり、協議が難航する原因になります。
特に相場感が共有されていないと「安く売りすぎではないか」「自分以外の誰かが得をしているのではないか」という不信感が生じやすくなります。
複数の不動産会社から査定を取り、客観的な相場観を共有するようにしましょう。
第三者である不動産会社から説明を受けることで、相続人間の感情的な対立を和らげる効果もあります。
土地の境界や権利関係が複雑で調査が難航する
土地の境界や権利関係が不明確なままでは、売却時に買主とのトラブルが起きる可能性があります。
古い土地や農地は登記簿と実際の土地利用状況が一致しないまま、長年経過しているケースも少なくありません。
隣家や都道府県とのやり取りが必要になることもあるので、土地の調査には早めに着手することをおすすめします。
相続した土地の売却について専門家に相談した方が良いケース

相続した土地の売却について、専門家に相談したほうが良いのは、以下のようなケースです。
- 共有名義の整理が必要なケース
- 相続税などの節税対策が必要なケース
- 無道路地や農地など買い手がつきづらい土地の場合
ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
共有名義の整理が必要なケース
相続した土地が複数の相続人による共有名義になっている場合、売却前に名義整理を行う必要があります。
共有名義では全員の合意がない限り契約が成立しないため、手続きが煩雑になります。
このようなケースでは相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が土地を取得するかを決定するか、または売却して現金で分配するかを話し合うことになります。
話し合いが難しい場合、連絡が取れない相続人がいる場合は専門家を介することも検討しましょう。
相続税などの節税対策が必要なケース
相続した土地に対して相続税が発生している場合は、売却と並行して節税対策を行いましょう。
相続から3年10か月以内に売却することで適用される取得費加算の特例など、期限が区切られているものも少なくありません。
小規模宅地等の特例や、3,000万円特別控除の適用条件も確認が必要です。
こうした特例は要件が細かく定められているので、税理士に相談しながら進めると安心です。
無道路地や農地など買い手がつきづらい土地の場合
無道路地や農地、市街化調整区域にある土地は、一般の住宅用地と比べて買い手が見つかりにくいのが実情です。
こうした土地を売却する場合は利用方法を工夫したり、地元の事情に詳しい不動産会社に依頼しましょう。
農地の場合は農地法の許可が必要になることもあるため、売却手続きが通常より複雑になります。
売却活動に時間がかかることを見越して、早めに準備を始めることが重要です。
相続した土地の売却でよくある質問

相続した土地の売却でよくある質問は以下の通りです。
- 相続した土地はすぐ売るべき?
- 税金の申告はいつまでにすれば良い?
- 売却に失敗したらどうなる?
ここからは、それぞれの質問に回答していきます。
相続した土地はすぐ売るべき?
相続税の申告期限や固定資産税の負担を考えると、早めに売却を検討するメリットは大きいでしょう。
特に相続税を納める必要がある場合、現金化を急ぐことで納税資金を確保しやすくなります。
ただし、価格を焦って決めると相場より安く売却してしまうリスクもあるため、準備と調査は慎重に進めることが大切です。
税金の申告はいつまでにすれば良い?
相続した土地を売却した場合の譲渡所得税は、売却した年の翌年の確定申告で申告します。
相続税を納めている場合、取得費加算の特例を適用するためにも期限を守ることが重要です。
相続税の申告は相続開始から10か月以内、譲渡所得の申告は売却した年の翌年の3月15日までと法律で定められています。
No.4205 相続税の申告と納税「申告の期限と方法」
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
引用元:国税庁「相続税の申告と納税」
なお、相続税の申告・納税義務は、相続財産が基礎控除額を超える場合に生じます。
基礎控除額は法定相続人の数等に応じて計算されます。
売却に失敗したらどうなる?
買い手がつかず売却が長引いた場合でも、固定資産税や管理費用は発生し続けます。
長期間売れない場合は、価格を見直すか、土地の活用方法を考えるなどの方向転換を求められることも。
いずれの場合も固定資産税や維持費用を節約する対策は、早めに取り組むことをおすすめします。
相続した土地の売却はプロにおまかせください

相続した土地をどのように売却するかは、相続人にとって悩ましい問題です。
故人から託された大切な土地を適正価格で売却するなら、地元で数多くの販売実績を積んできた静鉄不動産におまかせください。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは相続開始から土地活用、売却まで一括で支援する「相続ワンストップサポート」を提供しています。
各分野の専門家が連携し、安心・確実な相続を実現します。
相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ


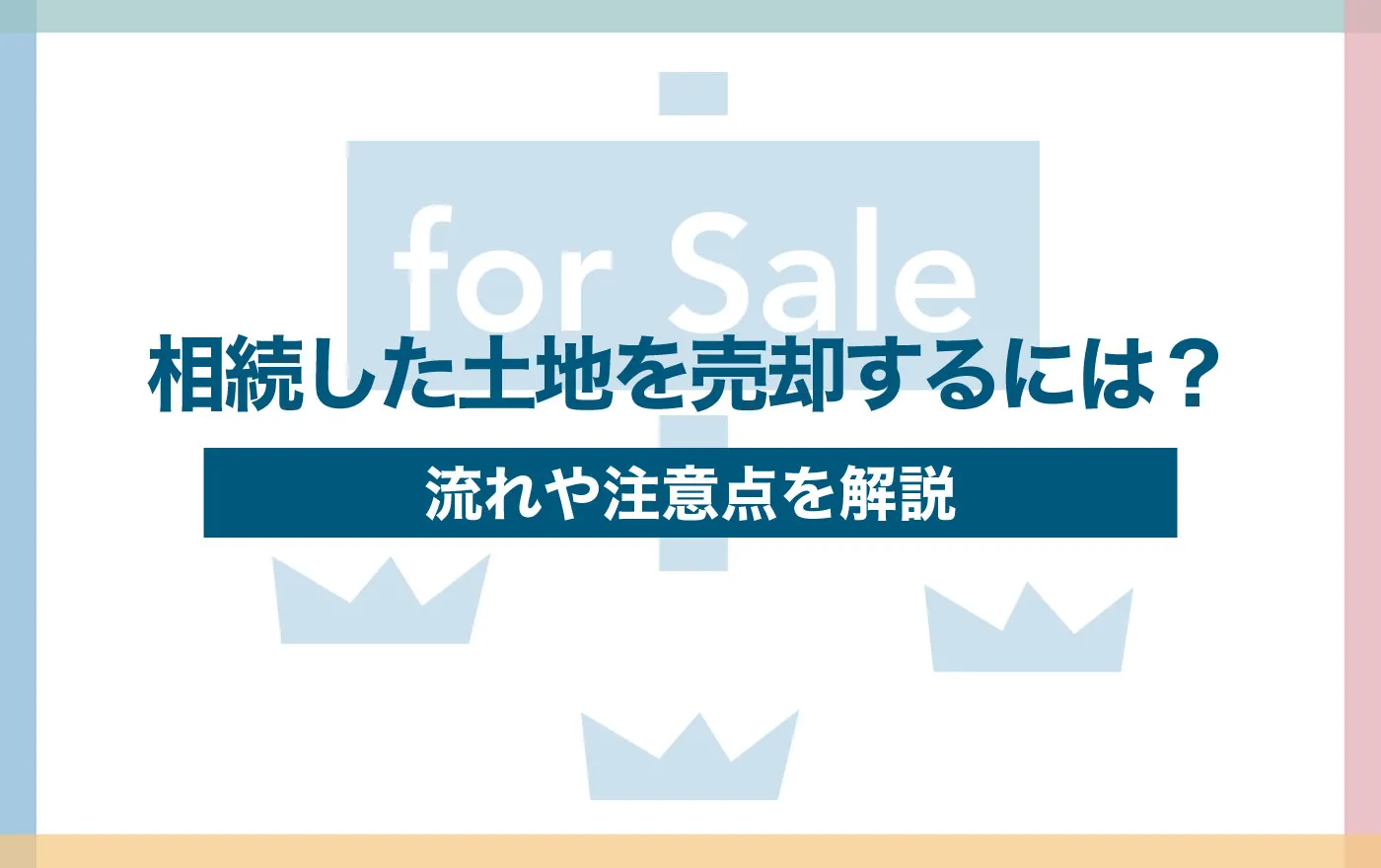


コメント